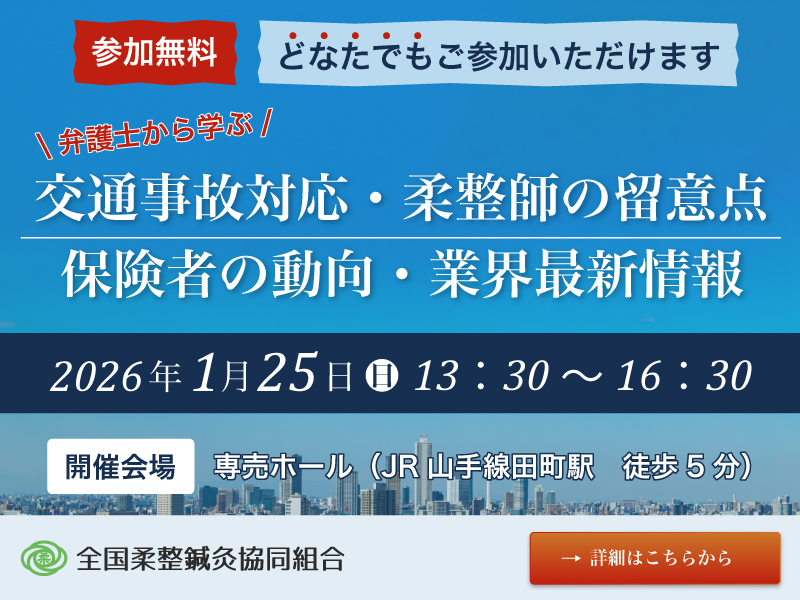Q&A『上田がお答えいたします』 施術管理者が「飛んで」しまったら
2019.06.25
Q.
整骨院の開設者です。施術管理者が無断欠勤しており連絡がつきません。別のスタッフにはメールで「俺、辞める!」と連絡があったようです。
A.
今すぐ連絡をとり、勤務継続の意思を確認すべきでしょう。全く連絡がつかないなら、早急に施術管理者を変更しなければなりません。新たに施術管理者になる柔整師を探すのか、他に勤務している柔整師を施術管理者にするのか、色々と考えがあると思いますが、重要なのは施術管理者になるための二つの要件、「1年以上の実務経験」と公益財団法人柔道整復研修試験財団が実施している「2日間の研修」を満たした者がすぐに見つかるかどうかです。
昨年4月から実施されているこの新要件ですが、当初「これは養成施設の新卒者にとっては打撃かもしれないが、既に開業している者は問題ない」などと言う開業柔整師がたくさんいました。私は「そうではない。開業柔整師こそが大打撃を被ることになる。なぜなら新たに施術管理者を任命できなくなるからだ」と声を上げ、反対すべきだと業界に訴えかけましたが、結局実施されてしまいました。「1年の実務経験」は結構クリアしている者も多いと思われ、新人柔整師も1年勤めるだけでよいのですからそれほど問題ではありません。しかし「2日間の研修」が難題です。開催回数が少ない上、インターネットでの受講受け付けもすぐ定員に達して打ち切られるという実態にあります。今頃になって「これでは療養費が請求できない」「保険を取り扱えない」という柔整師の悲鳴が聞こえてくるようになりました。
柔整療養費検討専門委員会でこの仕組みの導入を図った委員たちは、施術管理者になることが困難となった今、競合する同業者がどんどん廃業していき、その様を喜んでいることでしょう。保険者も、柔整師が療養費を取り扱えずに自費に移行していく実態を見てこれまた喜んでいるはず。「全て計画通り!」といった感じでしょうか。試験財団も、これだけ受講希望者が不平不満を漏らして改善を訴えても、抜本的解決策を検討しません。なぜならばこれでよいと思っているからです。全ては、国が音頭を取っている組織による施術管理者数抑制策であり、狙いはもちろん療養費削減です。今更騒いでも時すでに遅し。今後も改善はされないでしょう。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。