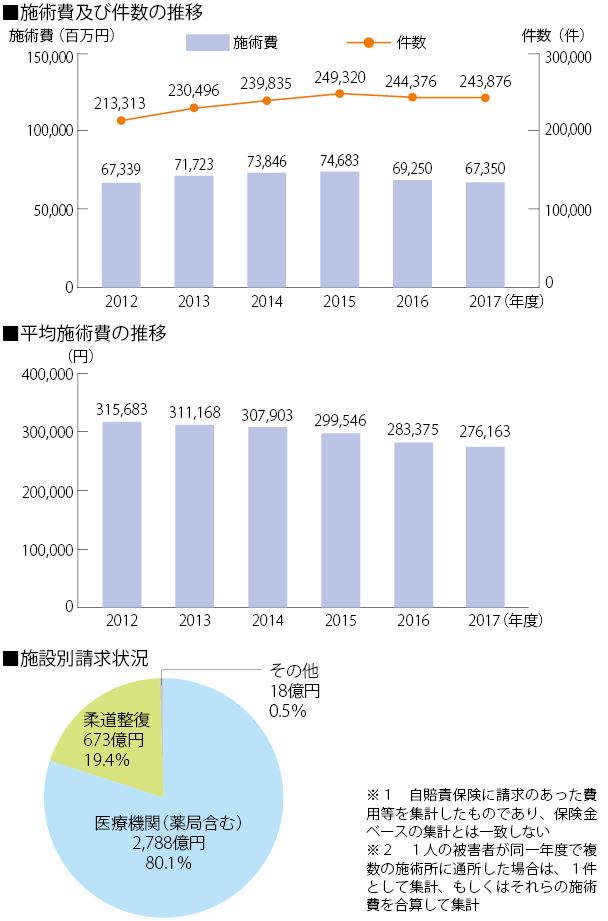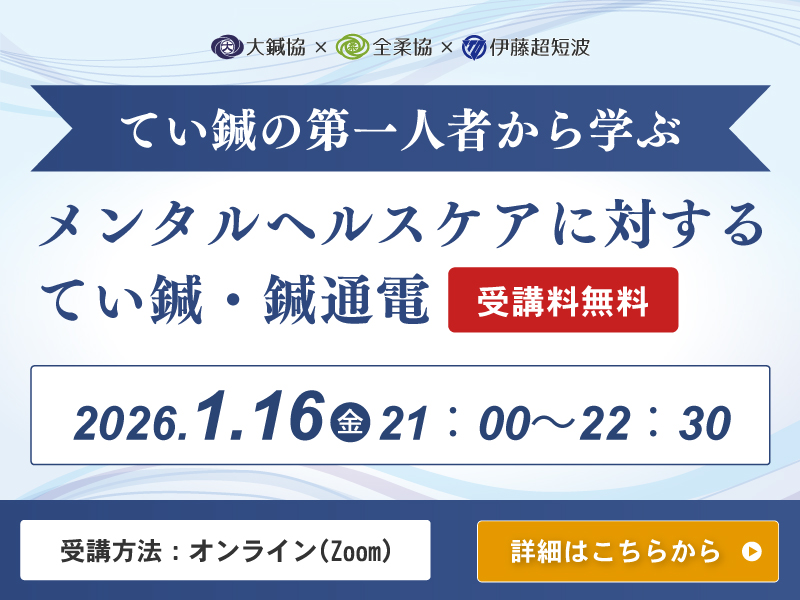連載『織田聡の日本型統合医療“考”』119 健康情報指導士講習会を開催!
2019.07.25
私が代表を務める健康情報連携機構主催で、「健康情報指導士 Ⓡ(Health Informatics Educator Ⓡ)講習会」を9月29日に神戸で行います。令和元年度では2度目となる講習会です。巷に溢れかえる健康情報を適切に見極め、患者さんに伝える能力等が求められる昨今、あらゆるヘルスケアに関わる人々が、最低限知っておくべき「医療理念」「医療情報」「医療連携」について学べます。そして、関西では初の開催となります。
私は先日、健康情報連携機構として中国・上海へ出張してきました。上海市中西医結合学会、上海市医師協会中西結合医師分会の役員のほか、上海浦東大学教授で整形外科医である付属病院副院長と面談。当機構の活動には大変興味を持っていただきました。さらに上海の隣の蘇州に移動し、既にオープンしている中医のクリニックと私が開発に携わった『ラクリス』(微弱電流を利用したあん摩・マッサージが可能となる手袋)のサロンが一体となった施設も視察してきました。
今回、上海では特に学術的及び臨床的な交流を深めることを念頭に、浦東大学の研修医を日本の医師が教育したり、中国の中医学を日本の鍼灸師や学生が学べたりする場を設けるといったことで合意をしてきました。そして、この秋にはラクリスの講習会を上海で開催する計画です。また、浦東大学でも解剖実習を行うことができるよう調整を進めています。日本の解剖士の資格を持つ歯科医師が中心となり、日本の制度や倫理に基づいた非常に質の高い実習を行う予定です。近くご案内しますのでご期待ください。当機構は世界が見守る日本の医療危機に対応するための活動を続けていて、フィンランドやスペインなどの欧州、中国やタイなどのアジアといった国際的な活動の幅を広げています。
さて、8月2日には「カル・リプケンU12世界少年野球大会」が開催されます。当機構は日本代表に帯同し、少年球児たちの医学的支援を行います。日本の4連覇がかかっていますので、しっかりケアをしてきます。当機構は今後とも継続して全国の少年野球リーグを支援していきます。そこで、この少年球児たちや親御さんたちを日頃から後方支援していただけれる医療機関や治療院を当機構から紹介していくことになります。ご興味がおありの治療家の先生方は、健康情報連携機構(https://www.health-info.or.jp/)にお問い合わせください。
【連載執筆者】
織田 聡(おだ・さとし)
日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事
医師・薬剤師・医学博士
富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。