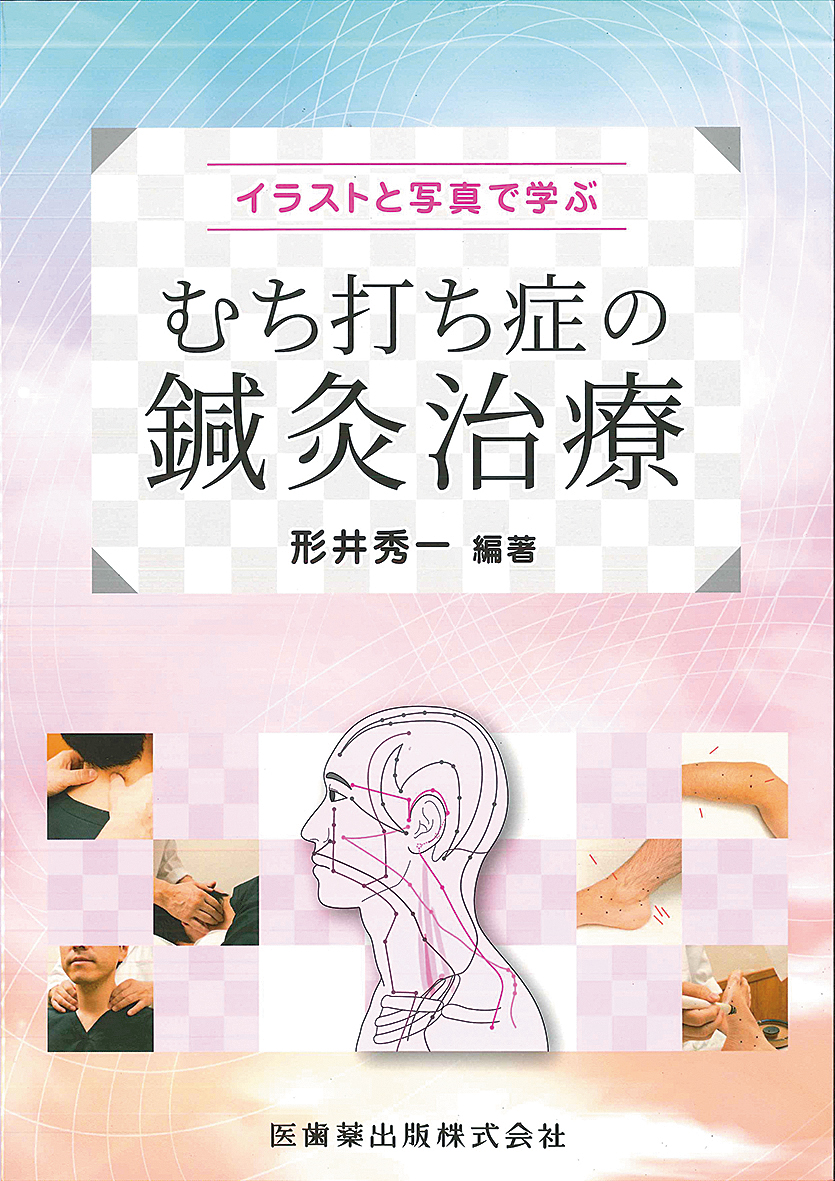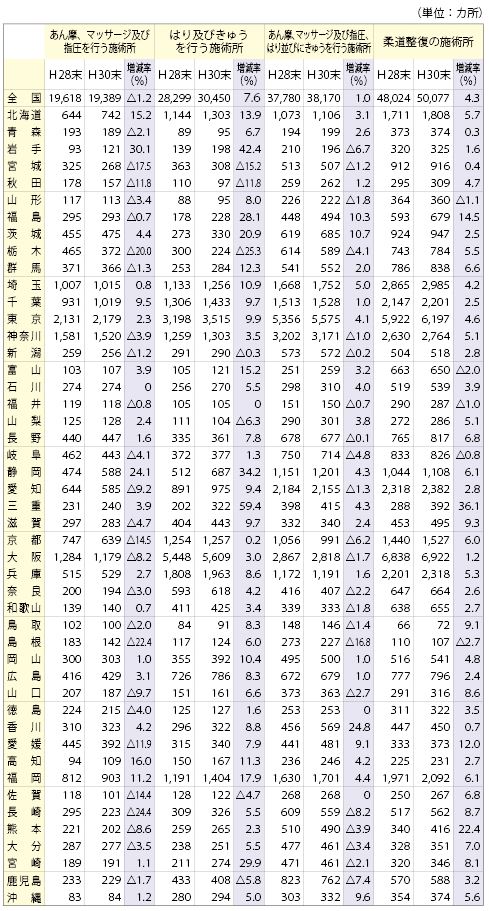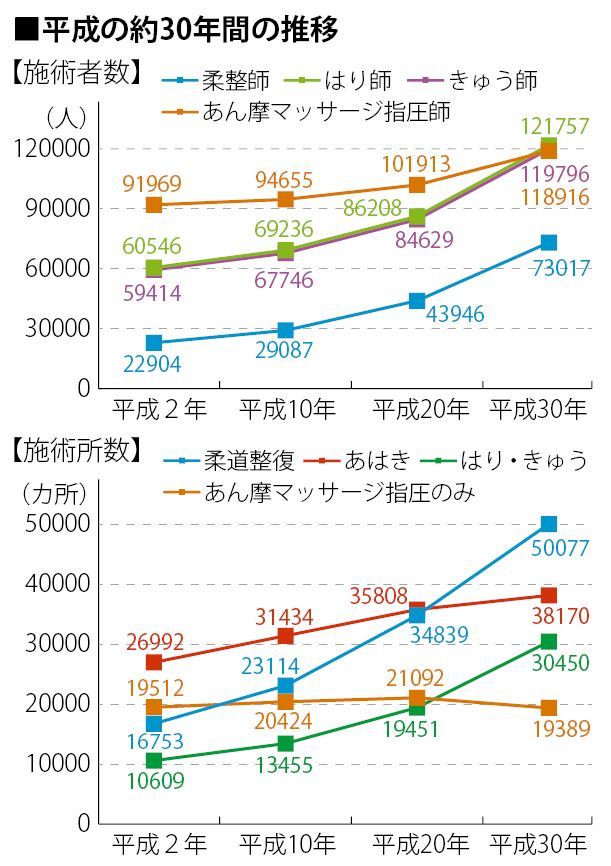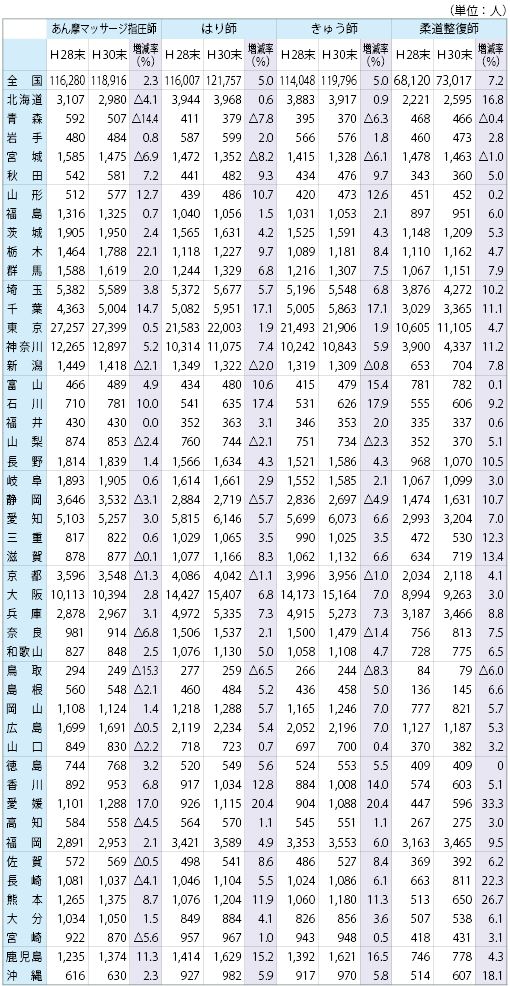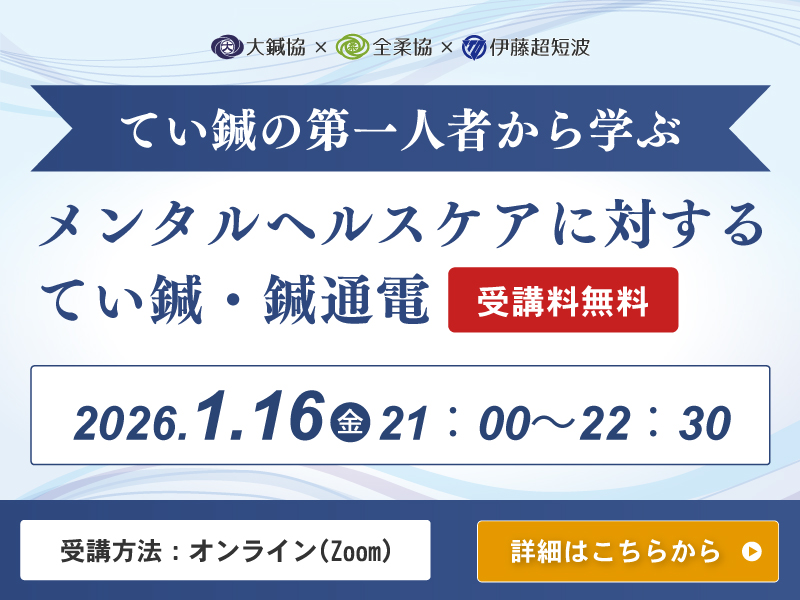連載『織田聡の日本型統合医療“考”』125 「公益資本主義」を医療に持ち込むには
2019.10.25
先日、東京の日本橋で開催された「ワールド・アライアンス・フォーラム円卓会議」に参加してきました。テーマは『公益資本主義2050年の国家目標―天寿を全うする直前まで健康でいられる社会の実現』。日本医師会の横倉義武会長、甘利明元大臣、石破茂元大臣も参加されていました。 2人に1人は癌になるという日本の現状を踏まえて、癌になっても元気に、事故でけがをしても元気に戻れる社会を、認知症にならず、死ぬ直前まで元気にいられる社会を実現するためには、技術・制度革新、そしてそれを支えるエコシステムの構築が大切である、そしてエコシステム構築には所得が倍増しなければならない、そういう流れで話は進みました。
アライアンス・フォーラム財団代表の原丈人氏の掲げる「公益資本主義」では、会社は株主のものではないといいます。会社が事業を通じて生み出した「公益」を株主だけでなく、会社を支える「社中」(会社、社員、顧客、仕入先、地域社会、地球)各位に公正に分配することが、本来あるべき資本主義の姿であると考えられています。原氏は、経済財政諮問会議に招聘され、今では内閣府本府参与を務めていますので、この考え方は政府への一定の影響力があると考えて良いです。 公益資本主義の考え方を医療へと応用するに当たり、社中として、医療機関、医療従事者、患者、製薬メーカー、地域医療、地球を考えた時、果たして公益は公正に分配されているでしょうか? 公益「資本主義」を考える前に、医療は「計画経済」の側面が強く、現場は非営利であることが求められ、技術革新が起こりにくい土壌であることを踏まえる必要があります。「公益」=「医療サービス」なのか、「利益」なのか(おそらく両方であると原氏は考えていると思いますが)。医療技術の発展には大きな開発資金が必要です。フォーラムで議論された技術革新の多くも、資金が必要なものばかりでした。医療革新が起きたとしても、その技術は公益であるとして価格が固定されます。利益を生むことを非難される医療経済の現状では、メーカーは開発費用を思い切って拠出しづらく、既に公益性の高い医療では公益資本主義は成立しないように思います。そもそも、現状では持続可能なエコシステムは構築できません。
公益資本主義を医療に持ち込むのならば、「タスクシフト」と「サービスの適正な分配」が必要だと私は考えます。タスクシフトとは、今まで医師しかできなかったことを医師でない人が担当できるようにすること。病院でしかできなかったことを病院外でできるようにすること。そういう技術革新こそ必要なのです。サービスの適正な分配とは、オーバースペックとなっている医療の現場で、適正なサービスが受けられるように制限することです。この流れは必ずやって来ると私は考えています。
【連載執筆者】
織田 聡(おだ・さとし)
日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事
医師・薬剤師・医学博士
富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。