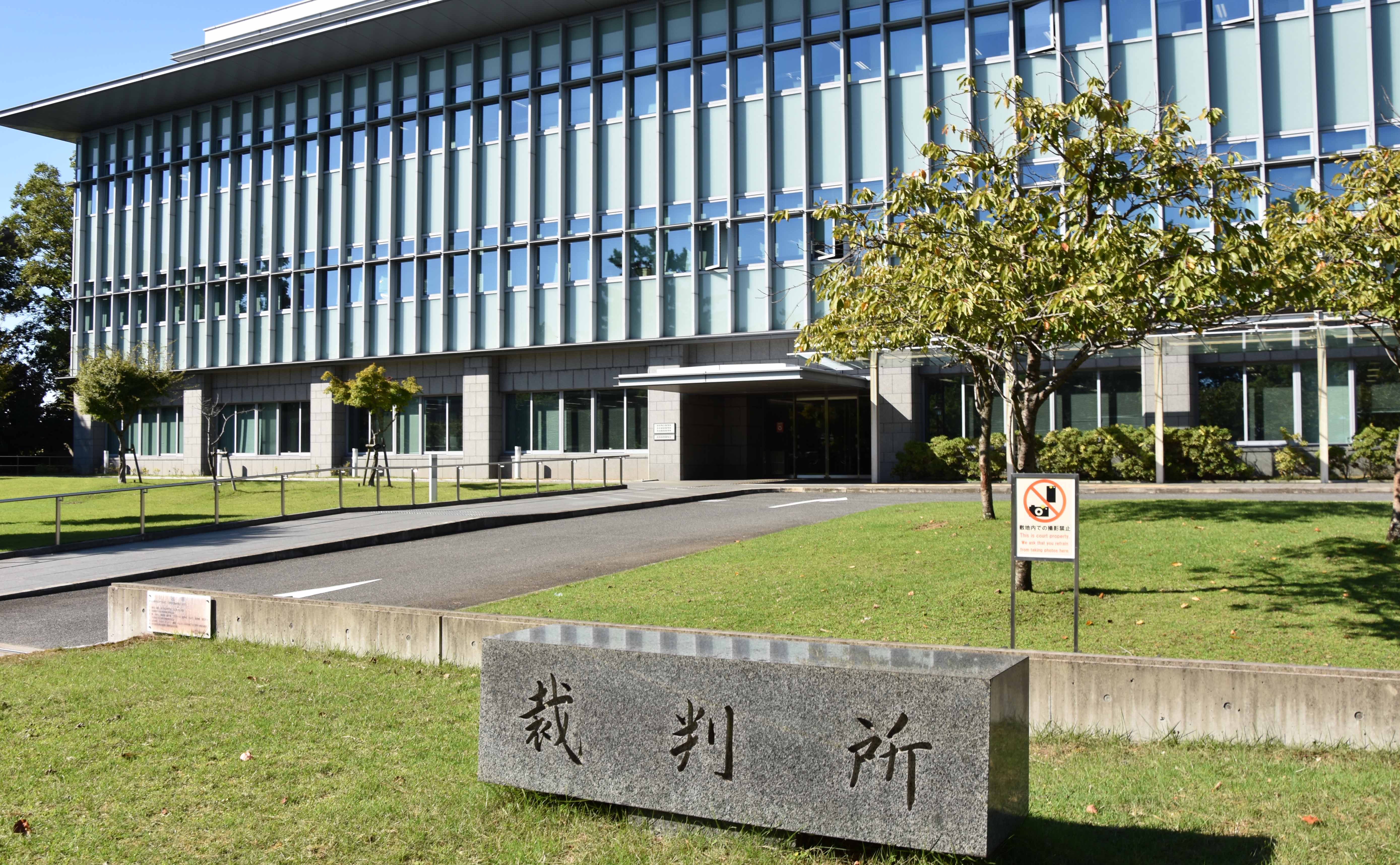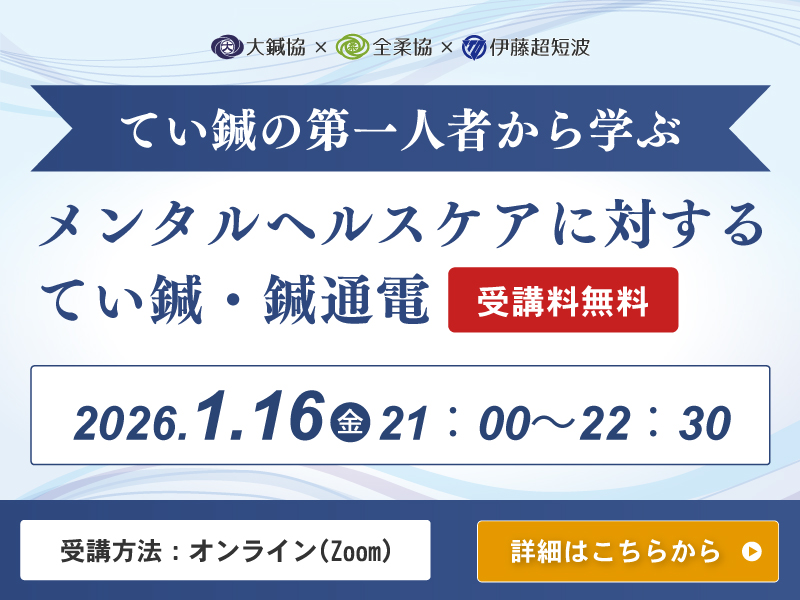『医療は国民のために』285 「非医業類似行為」を持ち出して、何がしたい?
2019.12.25
11月に広告ガイドライン案が厚労省から提示され、今年度末のガイドライン策定に向け、「あはき師及び柔整師等の広告に関する検討会」もいよいよ詰めの作業といったところだろうか。ここまで、施術者側と医師会・保険者側の言い分は相容れず、電話相談で日々患者の苦情等に接している患者団体からは柔整・あはき業界に否定的な発言も飛び出している。多少は致し方ないのかもしれないが、ガイドライン案で急に持ち出された「非医業類似行為」だけは絶対に許してはならないと警告しておきたい。
厚労省の考えでは、「非医業類似行為」でアロマテラピー、リフレクソロジー、整体、カイロプラクティック等を一括りにし、無資格者もガイドラインに適用して、決して放置などしていないと主張したいのだろう。そして、もう一つの狙いとして、あはき・柔整こそが「本当の医業類似行為」であると特定したいのだろう。
だが、私が過去に何度も述べてきたように、医業類似行為とは「よく分からない温熱療法や電気的物理療法」などを指し、「インチキ療法やペテン、まがいもの」といった侮蔑的といえる意味合いが強いものだ。少なくとも国家資格者の業務を指す訳がない。
しかも、本来あはきと柔道整復は「医業の一部」であって、医師法上は医師が行う医業において、柔整師やあはき師がその本来業務を行うに当たっては「限定解除」されているのである。さらに言えば、整体やカイロプラクティックは、法令上は「あん摩・マッサージ・指圧」の「指圧業務」であり、整体師やカイロプラクターがあん摩マッサージ指圧師の免許を取得しさえすれば、何の問題もなく施術行為ができるのだ(免許を持たず、整体・カイロを行うことを正しくは「無資格施術」という)。
ところが、整体師やカイロプラクターは免許を取りたがらず、国も野放しにしてきたことで、無資格問題が大きくなり、ここにきて、今度は「非医業類似行為」を定義したいという。広告検討会は歴史的な沿革を何も知らない方々の集まりなのであろうか。
ちなみに、「医業類似行為」と似たような用語で「医療類似行為」がある。こちらは医療を行うのは「医師のみ」であるが、医師が全てを行うのは事実上困難であることから、国家資格を得たそれぞれの専門職スタッフがパラメディカルとして医師を支え、医師の指導監督の下、医療を提供するとの考えに基づき定義されている。あはき・柔整は、独立開業資格であって、医師の指導監督を受けないということが前提だが、「医療類似行為」とされることはあろう。
しかしながら、本当に「非医業類似行為」という造語を定義するのであろうか。「末代までの恥」となってしまうことを案じてやまない。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。