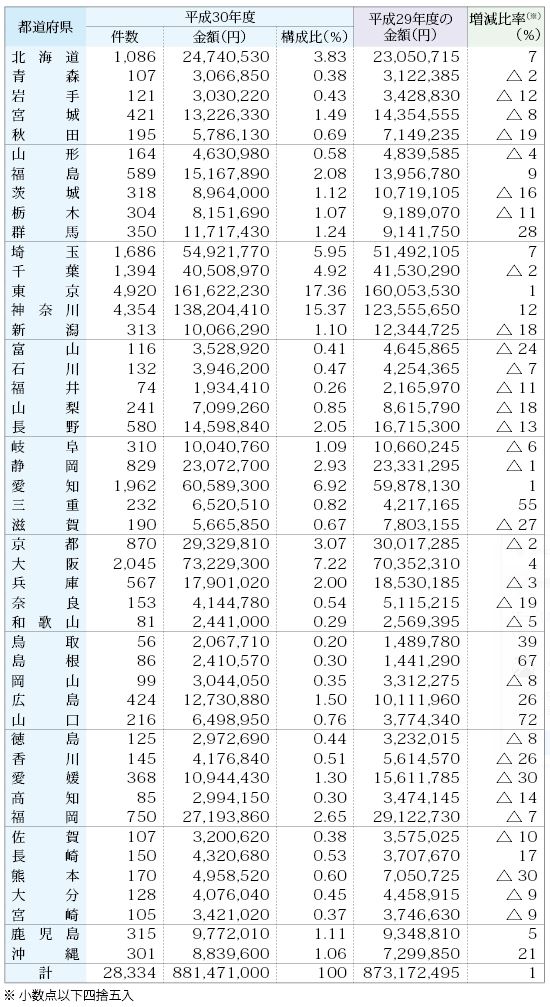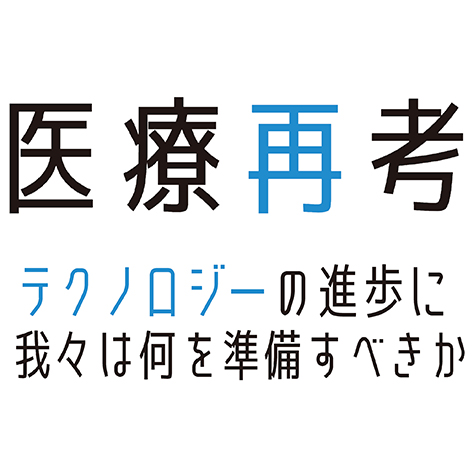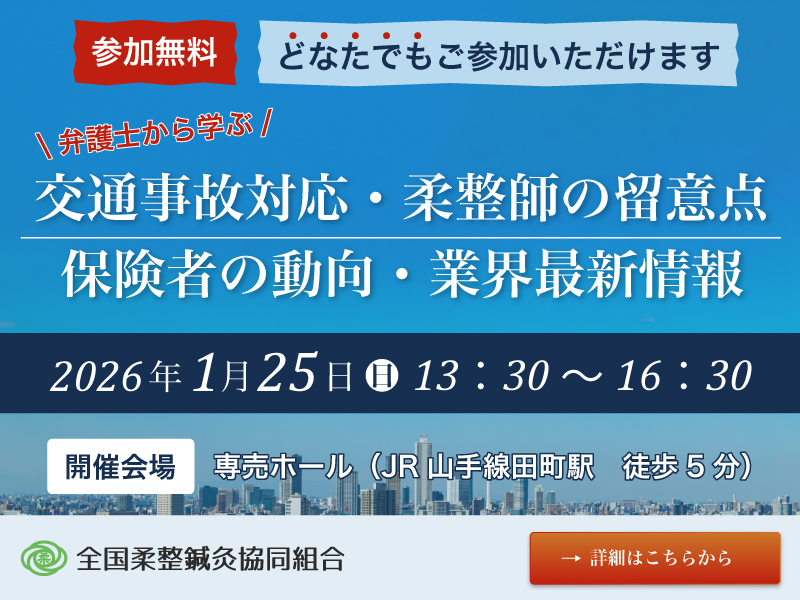セミナー『次世代に繋げたい鍼灸治療』 腹診と背部で全体治療
2020.02.10
―「僅三針法」の紹介も―
セミナー『次世代に繋げたい鍼灸治療―一見は百書を凌駕す』が1月12日、13日、大阪市内で開催された。鍼灸治療による疼痛治療研究会主催。
薬剤師で鍼灸師の南利雄氏(壺中天薬局・南鍼灸院)は、江戸時代の医師は実証主義で、「万病一毒説」を唱えた吉益東洞は陰陽五行説を否定していたと説明。現代でも、臨床においては無理に五行に当てはめることなく全体で診て治療に臨むべきだと説いた。江戸期の医書には脈診の記載は少なく、腹診が重要視されていたと指摘。脈診よりも腹診の方が分かりやすく誰もが習得しやすいとして、腹診と背部を基本とした全体治療を指南した。「一つの道具だけでは家が建てられないのと同様に治療道具にも種類があった方が良い」と解説。火鍼や長針、員利鍼といった臨床で実際に使用している鍼を実技を交えて披露し、細絡刺絡や皮膚刺絡なども行った。また、「鍼灸師にお勧め」の書籍として鍼灸素霊会編著『経穴の使い方 鍼の刺し方』や劉玉書編『刺鍼事故』などを紹介。『経穴の使い方 鍼の刺し方』は経絡治療の大家であった上地栄の講義をまとめたものだが、脈診よりも腹診を推奨している点が興味深いと述べ、『刺鍼事故』は中国の草医、いわゆる素人による事故例集だが、防止策や解決策も掲載されており参考になると話した。
循環器内科医の西田晧一氏(西田順天堂内科院長)は、数十年に及び鍼灸治療を臨床に取り入れてきた経験から、疾患によっては鍼灸でしか治らないものもあると説明。中国に起源を持つという、わずか三つの配穴で全身を治療する「三針法」に独自のアレンジを加えた「僅三針法」を紹介した。僅三針法は整形外科的疾患から内科的疾患にとどまらず、鬱病や認知症といった精神疾患にも効果があると解説。難病とされる線維筋痛症の原因は患者本人も自覚していない持続する精神的緊張にあると指摘し、僅三針法でその緊張を取り、付随する身体症状にも用いて症状が寛解した症例を提示した。
ほかに、「臨床歴70年」の松林康子氏による実技や佐藤崇司氏(千葉大学大学院医学研究院整形外科学)の研究発表が行われた。