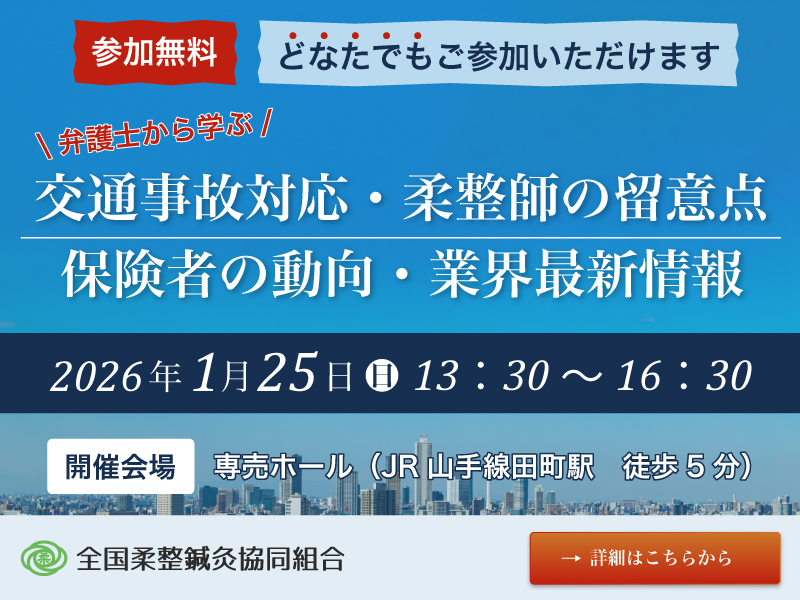連載『未来の鍼灸師のために今やるべきこと』24 鍼灸師のブランディングを考える
2019.01.10
1088号(2019年1月10日号)、未来の鍼灸師のために今やるべきこと、
これまで未来の鍼灸師のために行うべきことについて、様々な角度から考えてきました。高齢者人口の増加と生産人口の減少、医療費の高騰と枯渇などの社会問題を加味すると、医療は「治療」から「予防」にシフトしていくことに、疑いの余地はありません。そして、医療の目的が「治療」の場合はそのゴールは病気のない状態、いわゆる「健康」にありますが、予防の場合は「健康」であることが前提のため、そのゴールも「健康」の先にある「幸福」となります。それを踏まえた上で、未来に向けて「鍼灸」というブランドを再構築する必要があるでしょう。
ブランドとは、鍼灸に対するイメージを指し、「鍼灸はこういうものだ」という一般の人のイメージ=ブランドイメージと、「鍼灸はこうであると思われたい」という鍼灸師の願望=ブランドアイデンティティーの二つからなっています。そして、このイメージとアイデンティティーを一致させる「ブランディング」に、多くの企業や業種が力を入れています。例えば、鍼灸院の理念にはよく、「地域の健康に寄与する」や「患者を笑顔にする」といった言葉が掲げられていますね。これは鍼灸師が、「健康」や「幸福」などをアイデンティティーとしているということです。これは、今後の医療の流れを考えるととても時流に合った内容だと言えると思います。
さて、「健康」や「幸福」といった単語で、インターネットの画像検索を試してみて下さい。太陽の光を浴び、伸び伸びとした画像や、自然の中でリラックスしている画像が表示されると思います。これが「健康」や「幸福」の画像的なイメージです。一方、「鍼灸」、もしくは「はり・きゅう」で画像検索すると、どうでしょう。鍼の画像、鍼灸院の看板画像、鍼灸院の先生の顔画像などがほとんどです。これはホームページの閲覧数に応じて選ばれてきた画像であるため、鍼灸師側が作ってきたアイデンティティーであると思われます。そう考えると、一般の人が抱く健康や幸福のイメージと、鍼灸師が作り出したアイデンティティーは大きく異なっており、ブランディングの失敗が分かります。なお、「ヨガ」や「アロマ」を検索すると太陽の光を浴びて伸び伸びとした人の画像や、自然の中で光を浴びる植物の画像が多く表示されます。これらは「健康」や「幸福」のイメージと近く、イメージとアイデンティティーが一致しているためブランディングに成功していると言えます。
これはホームページの画像検索という方法を利用した一例ですが、世の中の至るところに鍼灸のブランディングの失敗を見て取ることができます。未来を創造して鍼灸のアイデンティティーを確立するだけでなく、一般のイメージと合うようにブランディングをしていくことが、これからはさらに必要だと思います。
【連載執筆者】
伊藤和憲(いとう・かずのり)
明治国際医療大学鍼灸学部長
鍼灸師
2002年に明治鍼灸大学大学院博士課程を修了後、同大学鍼灸学部で准教授などのほか、大阪大学医学部生体機能補完医学講座特任助手、University of Toronto,Research Fellowを経て現職。専門領域は筋骨格系の痛みに対する鍼灸治療で、「痛みの専門家」として知られ、多くの論文を発表する一方、近年は予防中心の新たな医療体系の構築を目指し活動を続けている。