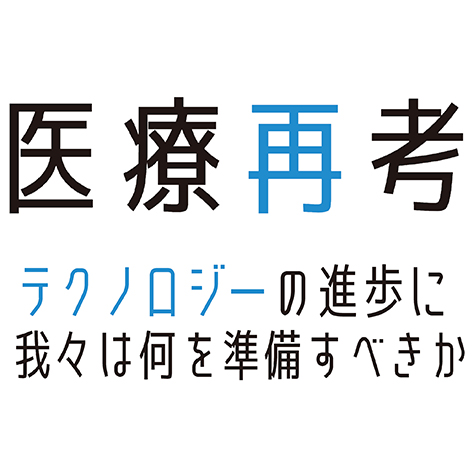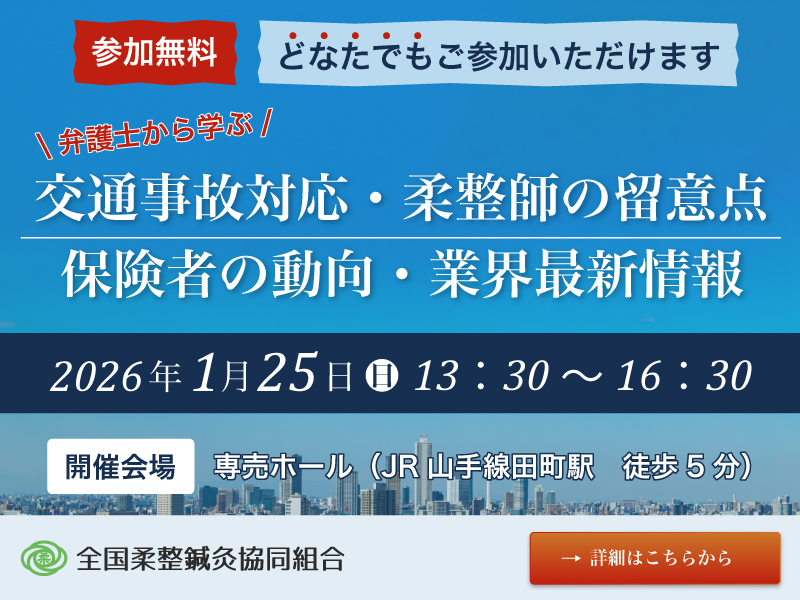『医療は国民のために』275 消費増税10%にかかる療養費の随時改定の議論を急ぐべし
2019.07.25
10月から消費税率10%への引き上げが確実視されている。これに伴い、郵便料金や電気代、ガス料金、鉄道運賃、タクシー料金、バス料金など、軒並み値上げされることになる。もちろん、柔整の物療機器や運動療法に関する機械類の購入費用、包帯や鍼、もぐさなど、施術に必要な物品の代金は軒並み値上がりし、鍼灸整骨院の出費は増加する。このような状況になることを見越し、当然、柔整・あはき療養費検討専門委員会に出席する予定の業界代表者は、議論のフレームワークを考えておくべきであるのは言うまでもない。
増税分に対しては、割に合う程度の療養費の引き上げは当然のことだ。「たかだか2%増など取るに足らないものだ」などとうそぶいていてはいけない。好戦的にかつ下品にまでも「取りに行く」覚悟が必要である。これも、「施術者の意見を反映させる者」として療養費検討専門委員会のメンバーに委嘱されているのだから、たとえ保険者側委員が「別に引き上げることもなかろう。引き上げるにしてもごくわずかで問題はない」と主張しても、しっかり対峙できるよう戦略を立てておくべきだ。医科本体に目をやれば、保険医療機関のコスト増加分を補てんする配慮が既になされる予定であり、初診料は60円引き上げられて2,880円となる。療養費も早急に消費税負担に見合う補てんを求めるべきなのだ。
5%から8%に引き上げられた前回(平成26年4月実施)の消費税増税にかかる改定は、医科の診療報酬が0.71%であり、柔整・あはき療養費も同様に4月実施ということで0.68%だった。従来までの「医科の半分の改定率」という悪しき慣習よりも高い改定だったが、これは柔整・あはき療養費の平成24年度料金改定が見送られたため(医科の診療報酬は平成24年4月から1.55%引き上げられた)、その分の“補てん”という要素が入り込んだものである。今秋の消費増税対応については前回の平成26年の時のような「積み残し」がないことから、「医科の半分の改定率」といった根拠の分からない決着だけは勘弁願いたい。ちなみに、今回の消費増税対応分の診療報酬の改定率は、医科でプラス0.48%、歯科と調剤を含めた全体ではプラス0.41%と既に決定済みである。
そもそも医療は非課税であり、鍼灸整骨院が負担する消費税部分は、患者に消費税という形で負担してもらうことにはならない。だからこそ療養費の施術料金に上乗せする必要があるのだ。高額な電気治療機器を購入する際の増税分や日々の鍼施術料金にまでかかってくる増税の負担を、一方的に施術管理者が負わされるいわれはない。
鍼灸整骨院の規模によっても大きくバラツキがあるのは承知の上で、2%分の補てんが適正・的確になるように、ぜひとも積極的な議論の展開を療養費検討専門委員会の業界代表者に期待する。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。