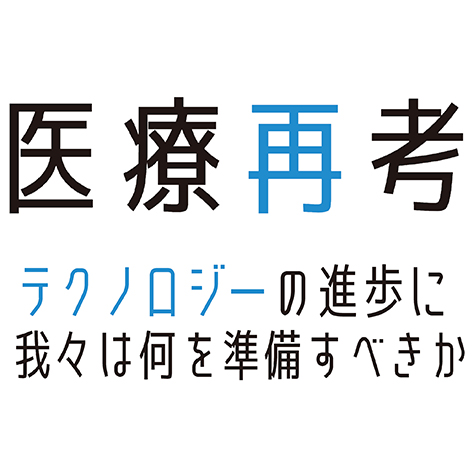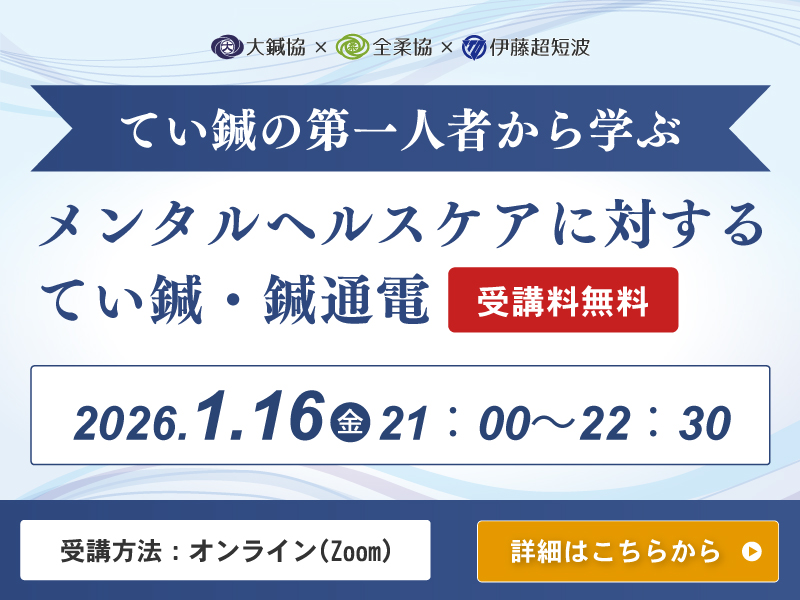Q&A『上田がお答えいたします』 医療助成費の還付の返還のタイミングは?
2019.10.10
Q.
今年から、あはき療養費にも受領委任の取り扱いが開始されましたが、いまだに従来の代理受領や償還払いの保険者も見受けられます。それぞれにおける、医療助成費も含む窓口で徴収した一部負担金を患者さんに返還するタイミングをご教示願います。
A.
療養費は施術費用の10割を患者・被保険者が支払って初めて請求権が発生し、被保険者が請求すると保険者から3割の一部負担金相当額を差し引いて支給されるものです。しかし、柔整療養費においては、協定・契約に基づき、実際には3割しか窓口で徴収しなくとも10割を患者さんが支払ったものと見なして受給権を発生させています。昨年まであはき療養費には受領委任の取り扱いが無かったので、患者さんが窓口でいったん10割を支払っておいて、後日、療養費が支給されたら施術所から7割を返還する、というケースも生じており、このわずらわしさも保険者の償還払いへの移行の理由の一つとされていましたね。さて、今後は受領委任の場合、現物給付として取り扱って良いのですから、窓口では療養費相当額、医療助成費分ともに全額受け取ることはありません(ただし、自治体によっては医療助成費額が一部負担金額に達しない場合がありますので、その際は差額のみを窓口で徴収します)。問題は代理受領の場合で、これは二つのパターンに分かれます。受領委任と代理受領を特段区別せず、「協定・契約の規程があるのが受領委任で、それが無いのが代理受領」程度しか認知していない保険者が大多数で、「受領委任だからこそ、窓口で医療助成費を含めて一部負担金しか払わなくても10割支払ったとみなされ、療養費の受給権が発生する」ことを理解していないのです。つまり代理受領と受領委任を混同している保険者については、最初から現物給付化して窓口徴収しなければ返還する問題も発生しないでしょう。
しかし、保険者の中には「10割の支払いがなければ受給権が発生しない」ことを知っている者もいて、これが通用しません。とはいえ、代理受領も償還払いも、窓口で医療助成費分をも含めて徴収しているのだから、これをどのタイミングで患者さんに返還するべきなのか、対応に迫られます。実は、明文化された決まりなどはありません。現実的には、①保険者や自治体から支給される前に適宜返還する、②支給を確認してから返還する、のいずれかになるでしょう。支給前に返還したほうが実務処理上簡便ですが、何らかの事情で支給されなかった場合はトラブルに巻き込まれる可能性もあります。支給後に返還した方がよろしいかもしれませんね。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。