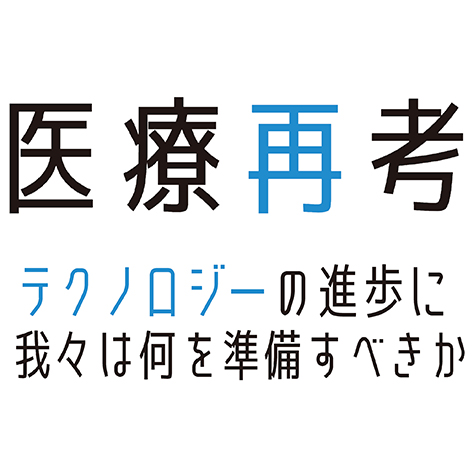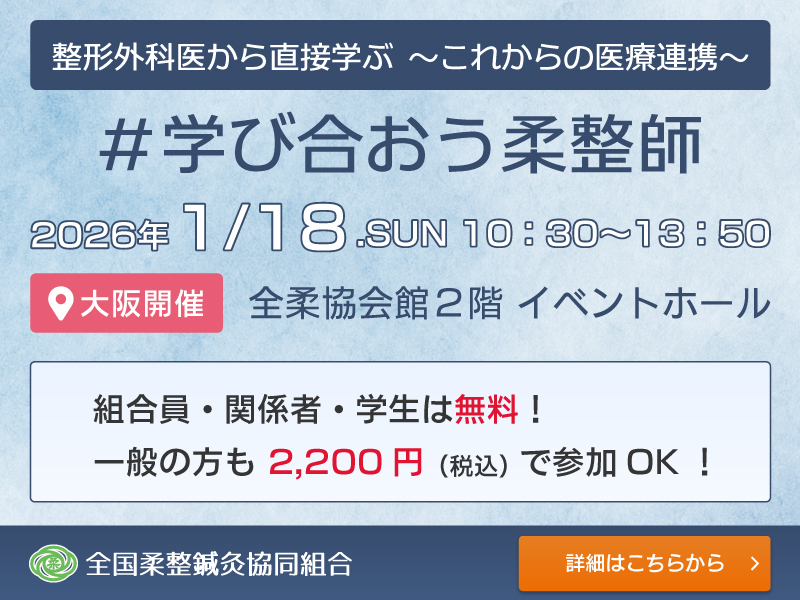連載『織田聡の日本型統合医療“考”』128 市販品類似薬の保険除外は、焼け石に水?
2019.12.10
1110号(2019年12月10日号)、紙面記事、織田聡の日本型統合医療"考"、
少子高齢化に伴う社会保障費の急増に対応するため、政府は「全世代型社会保障改革」の一環として、市販医薬品と同様の効果があって、代替が可能な薬(市販品類似薬)について、公的医療保険の対象から「除外」する方向で調整を進めているという報道がなされました。
財務省の資料によると、社会保障給付費は、1990年からの27年間で38.4兆円から94.9兆円へと2.5倍に増加しています。国民医療費の年齢階級別の金額(2016年)を見てみると、0~64歳の平均が一人当たり18.4万円に対し、前期高齢者(65歳~74歳)は平均55.3万円と約3倍で、後期高齢者(75歳以上)に至っては平均91万円と約5倍に跳ね上がります。このうち国庫負担金は、64歳以下の一人当たり2.6万円に比べ、後期高齢者は34.9万円と、負担が13倍も違います。2025年にかけて国庫負担が急増するのは明らかで、いかにその負担を軽減するのかに苦心しているのです。
しかし、医療費の急増は、高齢化のほかにも「医療の高度化」がその要因の一つとして挙げられています。有名なのはオプジーボで、年間で約3,500万円の費用がかかります。また、日本で保険収載されている高額医薬品として、ハーボニー(C型慢性肝炎治療薬)は12週間で約670万円、ステミラック(脊髄損傷に伴う機能障害の改善薬)は一回投与で約1,500万円、キムリア(急性リンパ芽球性白血病治療薬)も一回投与で約3,350万円です。今、承認申請されているゾルゲンスマ(脊髄性筋萎縮症治療薬)に至っては、米国価格で一回投与2億2,700万円。驚きの額です。もちろん、患者さんにとっては希望の光なのですが、国内の全ての罹患者に行き渡るには予算が許しません。そうなると、どう適応を考えるのかが難しいところです。こう考えていくと、冒頭で述べた、市販品類似薬を公的医療保険の対象外にしたところで、「焼け石に水」の感があります。
それよりも、私は最近よく聞かれる「医師の働き方改革」に注目しています。医師の時間外労働上限規制は「現実的でない」「医療崩壊だ」との批判の声も聞かれますが、「タスクシフティング」という考え方をもってすれば、全ての人にWin-Winの政策となり得ると思います。今まで医師でなければできなかったことを、医師以外の単価の低い労働力に担ってもらうことで、医師の報酬はあまり変わらず、仕事量を減らすことが可能となります。病院でしかできなかったことが、病院以外でできるようにする「技術」はたくさんあります。技術が制度を変える時期は、もうすぐそこまで来ているように思います。
【連載執筆者】
織田 聡(おだ・さとし)
日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事
医師・薬剤師・医学博士
富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。