連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』26 サピエンス全史
2020.06.10
まだ続く5月のヒマさの中で「ジタバタしても仕方ない」と、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史 上下巻』を3週間で読了したのですが、固定観念が根底から揺さぶられました。 (さらに…)
連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』26 サピエンス全史

連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』26 サピエンス全史
2020.06.10
まだ続く5月のヒマさの中で「ジタバタしても仕方ない」と、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史 上下巻』を3週間で読了したのですが、固定観念が根底から揺さぶられました。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』140 医療は戯言か?

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』140 医療は戯言か?
2020.06.10
全国で緊急事態宣言が解除され、コロナ自粛は継続するものの、飲食店などの営業も再開し、都心でも少しは日常に戻ってきた感じがします。
さて最近、友人の医師らがSNS上で話題にしていた書籍があります。 (さらに…)
連載『中国医学情報』183 谷田伸治

連載『中国医学情報』183 谷田伸治
2020.06.10
☆新型コロナウイルス肺炎患者の温灸法―中国鍼灸学会「指導意見」
中国鍼灸学会は、新型コロナウイルス肺炎患者の温灸法を発表(中国鍼灸、20年2期)。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「他の療法による費用を請求しないこと」とは 「自費」を認めないということ?

Q&A『上田がお答えいたします』 「他の療法による費用を請求しないこと」とは 「自費」を認めないということ?
2020.06.10
Q.
あはき療養費の受領委任の取扱規程19に「請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと」とあるのは自費メニューを一切認めないということでしょうか。
A.
そうではありません。「あはきの施術を療養費支給申請書で申請するに当たって (さらに…)
連載『汗とウンコとオシッコと…』190 Gravity

連載『汗とウンコとオシッコと…』190 Gravity
2020.06.10
なぜか今、カメムシが多い。元々カメムシには暖かい場所を好む性質がある。家の中に入ってくるのはそういう理由であり、奴らが多い時の冬は豪雪すると言われている。普通は秋口によく見かけるのだが、5月半ばからやたらと家の中に飛来して、悪臭で鼻をひん曲げてきている……。つまり、気候は秋口のようなモノというわけだ。紫外線が強い割には涼風が吹き、皮膚が焼けているのに口渇を感じない、というわけだ。しかも気温差が20度近くになり心臓や循環器に影響する。ましてやコロナ騒動で運動不足が助長させられて放熱がうまくいかず、熱中症のようになり救急車の搬送数が増える……。元気な人では関節腫脹や皮膚の痒みなどが出るか、寝違い様の体表が冷える割に中で熱がこもった腰痛や頸部痛などが現れやすい……。
「先生、昨日の朝から腰が痛くてね。ギックリ腰って感じではないんですけど……。まあ、田んぼに肥料を入れたんだけど、重たいものを持って捻った時のような腰の痛みじゃあないんですわ」
と、40代前半の農家の西田秀長という体格のがっしりした男性が来院した。話を聞くのは横転先生だ。 (さらに…)
連載『医療再考』16 社会構造の変化にどう対応するのか―BI時代における鍼灸治療の意味
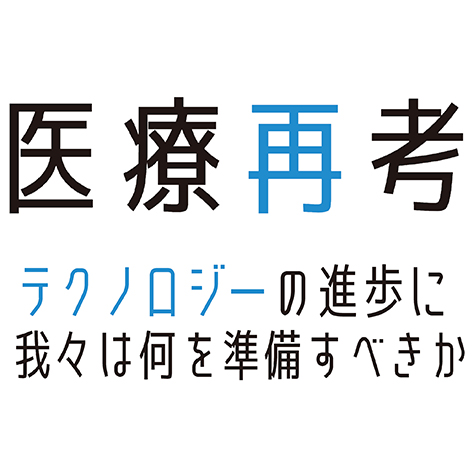
連載『医療再考』16 社会構造の変化にどう対応するのか―BI時代における鍼灸治療の意味
2020.06.10
今回はBI、ベーシックインカム(basic income)の話です。BIとは、最低限所得保障の一種で、政府が全ての国民に対して、最低限の生活を送るのに必要とされている額の現金を定期的に支給するという政策のことです。最低所得が保証されるなんて夢のまた夢のような気がしますが、人工知能(AI)が進歩・普及すると、仕事の多くは奪われてしまうかもしれません。そうなると、単純作業のような仕事の多くがなくなる一方、その分AIが価値を創出します。AIが普及した世界は「失業者は多いが、生産性が高い社会」となり、AIが稼いだ社会の富を再分配する方法として、BIが注目されているのです。 (さらに…)
今日の一冊 僕は偽薬を売ることにした

今日の一冊 僕は偽薬を売ることにした
2020.06.10
僕は偽薬を売ることにした
水口直樹 著
国書刊行会 1,980円
睡眠薬依存症の減薬に代替品として「偽薬」が役立つかもしれない。偽薬を与えることで「薬を飲み忘れた」と主張する認知症患者を安心させられるかもしれない――。薬学系の大学院を修了し、製薬会社の研究員を経て「偽薬を売る会社」を設立した著者は冒頭のような提案をしつつ、一方で「偽薬には効果があるのだ」とも主張する。プラセボ効果とは何なのか、なぜ「効く」のかを突き詰めていくと科学や科学に依拠する現代医療の限界が見えてくる。科学の申し子が、科学の向こう側を透視する「超問題作」。
『医療は国民のために』295 柔整療養費の受領委任における「復委任」に思う

『医療は国民のために』295 柔整療養費の受領委任における「復委任」に思う
2020.05.25
昨年末、大阪の整骨院グループが、事実と異なる柔整療養費の請求を組織的に行っていたとの疑惑が報じられ、業界外でも大きな話題となった。このグループ内の整骨院の請求が関連の請求代行会社で一括提出されていたことから、2月に開かれた厚労省の柔整療養費検討専門委員会で「復委任」が俎上に載せられ、今後議論が展開される見通しだ。
そもそも、この「復委任問題」とは何なのか。まず確認したいのが、受領委任の取り扱いとは、療養費の申請権者である被保険者(国保の場合は世帯主)に支給される療養費を柔整師(協定及び契約上では「施術管理者」)が受け取ることを認めた事務処理である。そして、被保険者等が柔整師に療養費の受け取りを委任し、これを受けてさらに施術管理者が自分の属する団体の長に委任することを「復委任」と言っている。
ここで留意すべきなのは、被保険者が窓口では3割しか支払っていない事実と、一部負担金相当額である3割を控除した7割が保険者から支払われることから、柔整師にしてみれば患者に残りの7割の施術料を請求できる債権(残金請求権)がある一方、支給された療養費はあくまで被保険者に帰属するものだから患者に返さなければならない(受領金返還債務)が、この債権と債務が同額であることに鑑みて、柔整師の手元において相殺することで、結果的に療養費が被保険者等に支払われたとする事務取扱いなのである。厚労省の通知によれば、施術管理者の元で相殺処理が完結しているが、実際は、療養費の取り扱いを団体の会長宛てに施術管理者がさらに委任しているのが一般的である。
そんな中、保険者が「団体の長(会長とか理事長とか)が受領することは、国の通知では全く触れていない」ので、冒頭のような不始末が起きたと決め込み、「国の通知どおりに施術管理者の受け取りのみを認め、復委任に基づく組織団体への入金を阻止すべし」と、専門委員会の議論の場で主張し出したのだ。確かに施術管理者が所属団体の長へ受り取りを再度委任することは、厚労省通知のあずかり知らないところで、あくまでも民法の規定に基づくものということになるだろう。協定や契約の当事者として、地方厚生局長や都道府県知事が復委任を認めないと言えるのかどうか、ここは民法上の解釈の問題であることから、法令解釈上許容されるのかどうかが今後議論されることになろう。
とはいえ、「協定」に論拠を置く「包括としての復委任」として、「契約」とは異なることを理由に、協定だけが引き続き各都道府県柔道整復師会(社団)の会長やその傘下に位置付けられる協同組合理事長宛てに療養費の送金を認められるとなれば、同一資格・同一免許にもかかわらず、国が「ダブルスタンダード」を認容することにもなりかねない。このような判断をしないとは思うが、通知に何の規定もない復委任を、この際、明確にしておく必要はあるものと考える。
ちなみに、保険者が「認めない」と豪語しているが、保険者は協定や契約の当事者ではないのだ。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。
連載『先人に学ぶ柔道整復』二十一 吉雄耕牛(中編)

連載『先人に学ぶ柔道整復』二十一 吉雄耕牛(中編)
2020.05.25
耕牛を訪ねた多くの一流学者たち
江戸時代に、オランダ語通詞でありながら「吉雄流外科」を興し、接骨家など多くの門弟を抱えていた吉雄耕牛は、医術(整骨も含む)のほか、天文学、地理学、本草学などを修め、蘭学を志す者にこれらを教授しました。今回は、耕牛の元を訪ねた学者たちを見てみたいと思います。
最も関係が深かったのは、オランダ商館付のスウェーデン人医師であるカール・ツンベリーだと言われています。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』139 「非接触」の新規産業の創出

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』139 「非接触」の新規産業の創出
2020.05.25
この原稿を書いている時点で、39県で緊急事態宣言が解除されて、残り8つの都道府県が継続しています。解除された地域の治療院は患者さんの戻りはどうでしょうか。ポストコロナの議論は気が早いと言われるかもしれませんが、既に社会では「ポスト自粛」の変化に気がついている人も多いと思います。もう元の世の中には戻らないだろうと感じている人も多いことでしょう。 (さらに…)
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』182 第5中足骨基底部骨折(下駄骨折)②

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』182 第5中足骨基底部骨折(下駄骨折)②
2020.05.25
竹本 晋史(筋・骨格画像研究会)
前回、第5中足骨基底部骨折、いわゆる「下駄骨折」について、超音波画像観察装置(以下、US)を用いて患部を観察した症例を紹介した。今回はその整復と経過観察について報告する。なお患者は50代の男性で、段差に気付かず足を踏み外し、左足関節を内反強制され負傷。昨年の12月13日に来院した。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「医科の半分」のままでは代わり映えせず

Q&A『上田がお答えいたします』 「医科の半分」のままでは代わり映えせず
2020.05.25
Q.
先日、柔整療養費の令和2年度の料金改定案が示されました。いつも思うのですが、プラス改定の実感が全くないような部分しか上がりませんよね。
A.
従来から「医科の改定率の半分」ということで料金改定枠があらかじめ設定されていて、今回は診療報酬のうち医科の改定率である0.53%の半分の0.27%。これでは思い切った引き上げなど到底できません。いつも影響率の小さな「骨折・脱臼、不全骨折」の整復料や固定料、後療料の引き上げにとどまるのは、引き上げに使える「財源」が少なすぎるからですね。
本来であれば、 (さらに…)
連載『食養生の物語』84 五月病の兆候

連載『食養生の物語』84 五月病の兆候
2020.05.25
五月病が心配な時期になりました。五月病とは、4月からの入学や就職など新しい環境に適応しきれず、5月のゴールデンウイーク明け頃になって、精神的な症状が表れ始めること。医学的には「適応障害」あるいは「うつ病」に当たります。新型コロナウイルス感染拡大防止からの緊急事態宣言は多くの都道府県で解除されたものの、まだまだ前を向きにくい状況が続く今、こうした症状が長引く恐れもあります。 (さらに…)
連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』19 『ごはんの食べ方』

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』19 『ごはんの食べ方』
2020.05.25
東洋医学は、天と地に合わせて生きる考え方です。 (さらに…)
今日の一冊 人類と病 国際政治から見る感染症と健康格差

今日の一冊 人類と病 国際政治から見る感染症と健康格差
2020.05.25
人類と病 国際政治から見る感染症と健康格差
詫摩佳代 著
中公新書 902円
なぜ天然痘は根絶に成功し、マラリアとポリオはまだ根絶されていないのか。その背景にはワクチンや治療法の発見といった問題に加え、国際政治上の問題があった――。サーズ、新型インフルエンザ、エボラ出血熱、そして新型コロナウイルス。感染症のパンデミックは今なお頻繁に人類を襲い、恐怖と混乱に陥れている。そうした世界で、人類が健康を確保するために作り上げたのが病に対する国際協力体制、「グローバル・ヘルス」だ。WHO設立の過程、感染症との歴史を追いながら、その役割と限界を論じる一冊。
『医療は国民のために』294 厚労省が柔整の請求代行団体を「ファクタリング」と認めないのはヘン

『医療は国民のために』294 厚労省が柔整の請求代行団体を「ファクタリング」と認めないのはヘン
2020.05.10
一般に「ファクタリング」とは、他人が有する売掛債権を買い取って、その債権の回収を行うサービスを指す。医科などの診療報酬明細書では、保険請求する債権が保険医療機関の「お金」であるから、入金前に現金化する債権譲渡、いわゆるファクタリングは日常的にも行われ、また、これを専門に取り扱う金融商品も出回っている。 (さらに…)
連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』25 風が吹けば

連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』25 風が吹けば
2020.05.10
「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざがあります。一つの事象が全く予測できないところに影響を及ぼすという意味です。似たものに「バタフライ効果」というものがあり、蝶の羽ばたきが竜巻を起こす可能性もあるという意味です。コロナウイルスも最初は中国のごくわずかな患者から始まりました。どこかの国の指導者は、最初にタカを括っていたらその国は最悪の事態となりました。早々にロックダウンしたところは終息傾向が早まりました。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』138 ダブルループ学習

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』138 ダブルループ学習
2020.05.10
緊急事態宣言が延長されました。鍼灸院も接骨院も自粛対象から外れていますが、患者数が減っていると思います。医療崩壊を防げと言われますが、発熱を診ないような一般の医療機関も患者数が減っていると聞いています。そもそも医療機関は非営利を求められているので、それほど資金が潤沢なわけではないところも少なくなく、今後は自粛のための医療危機が生じるかもしれません。受診を自粛してもなんとかなるような患者さんで、薬局で薬を自費で買ってセルフメディケーションで事足りるのだと分かると、ある意味、医療機関でのその診療は過剰であったとも言えるわけで、ポストコロナの医療も変わってくるかもしれません。さて、患者さんは医療機関へ戻るでしょうか。 (さらに…)
連載『中国医学情報』182 谷田伸治

連載『中国医学情報』182 谷田伸治
2020.05.10
☆癌性疼痛(多発性骨転移癌)の鍼灸治療例
南京中医薬大学・魏心昶(しんえい)らは、腎臓癌術後の骨転移による癌性疼痛の鍼灸治療例を報告(中国鍼灸、19年4期)。
患者=男、72歳、退職した職工。2017年7月10日初診。
主訴=左右肋骨部と右側頭部の疼痛が反復し1年余り、この1カ月で悪化。
現病歴=2002年右腎臓癌が発見され、切除術後一般状況は良好。1年前歯の色が濃くなり、全身各所の疼痛を自覚、南京市第一病院の検査で多発性骨代謝異常が見つかり、多発性骨転移癌の可能性が考えられたが、放射線や抗癌剤治療を拒否。鎮痛剤(Tramadol)長期服用も効果なし。17年6月9日南京市中医病院のMRI検査:右第7・9肋骨、左第8肋骨、右肩甲骨に破壊、左第6肋骨前段に骨破壊に伴う皮下軟部組織腫瘤。
現症=左右肋骨部・右側頭部・背部の疼痛顕著(VAS:8~9)、四肢運動制限なし、活力不足、食欲少、排便正常、夜間疼痛顕著、睡眠に影響。舌尖紅、苔黄膩、脈弦数。
診断=西医:腎臓癌術後多発性骨転移、中医:骨瘤。
治療法=毎日1回、1クール5回(クール間2日休む)。
①仰臥位―0.25×40mmの鍼で、中脘・下脘・気海・関元・大横・足三里・三陰交・懸鍾・太衝・風池・右率谷に刺鍼。局部疼痛部位(左右肋骨部、右肩甲下角)に、直径10cmで上下左右4方向から15°で斜刺(深度30mm)。左右の足三里・懸鍾を各一対で通電(連続波・30Hz・約2mA)30分間。同時に湧泉に棒灸30分間。
②座位―大杼・肝兪・脾兪・腎兪の膀胱経に上向きで45°で斜刺10mm、捻転得気後、置鍼10分間。抜鍼後、膀胱経第1線の肺兪・心兪・膈兪・肝兪・脾兪・腎兪・大腸兪を上から下に直径5cmの竹製の吸い玉(閃缶)をかけ、皮膚を紅潮させる。
経過=1クール後、疼痛顕著に軽減(VAS:4~5)、食欲・睡眠も好転、鎮痛剤(Tramadol)減量(100~200mg→50mg)。2クール後、疼痛はたまにだけ(VAS:2~3)、食欲・睡眠は正常、鎮痛剤停止可能となり、歯の色浅くなる。3クール後、病状安定、疼痛目立たなくなるが、毎週3回の継続治療。17年11月10日、疼痛目立たず(VAS:2~3)、運動制限なし、食欲・排便は正常、夜間疼痛再発なし、MRI検査:骨転移部に変化なし。
☆癌性疼痛の常用穴
広西中医薬大学・唐翠娟(すいえん)らは、癌性疼痛の常用穴を分析(中国鍼灸、20年3期)。
方法=国内三つ、海外一つ のデータベースを用い、2008年1月1日~18年12月30日までの臨床文献を検索。
文献=中文67篇・英文1篇。内訳:多種癌41篇、肝臓癌9篇、胃癌6篇、肺癌5篇、乳癌4篇、卵巣癌・大腸癌・食道癌各1篇。
結果=穴位処方73首、穴位総数117穴(4回以上使用は40穴)。
①10回以上使用の穴名と回数―足三里65・内関55・太衝50・合谷48・三陰交48・阿是穴39・陽陵泉38・豊隆32・膈兪29・血海29・大椎23・肝兪22・中脘21・期門20・腎兪14・胃兪13・脾兪13・肺兪12・行間11・関元11・支溝10。
②経絡別の使用回数と穴数―膀胱経141回21穴・胃経121回13穴・肝経96回7穴・脾経91回7穴・大腸経61回6穴・心包経60回4穴・胆経54回11穴・任脈53回7穴・奇穴/阿是穴48回5穴・督脈34回7穴・三焦経23回8穴・肺経20回7穴・小腸経14回9穴・心経8回3穴・腎経5回2穴。
☆脳卒中後の手関節縮には梅花鍼併用
河北省中医院・王穎穎(えいえい)らは、脳卒中後の手関節拘縮には梅花鍼併用が効果的と報告(中国鍼灸、20年1期)。
対象=同院鍼灸科とリハビリ科入院患者72例(男35例・女37例)、平均年齢約61.5歳、平均罹患期間約58日。これをランダムに常軌群(リハビリ)・鍼併用群各36例に分けた。
治療法=1クール3週、計3クール。
①リハビリ―1)Bobath法:毎回20分間・毎日1回・毎週5回。2)日常生活活動能力訓練。
②鍼併用群―梅花鍼で手三陰経を手関節横紋下1寸→上3寸まで叩刺(80~130回/分、軽微な出血が限度)、2日1回・毎週3回。
観察指標=①自動的手関節背屈時の可動域(AROM)、②Fugl-Meyer 評価法(FMA)、③バーセル指数(BI)。
結果=①AROM:常軌群16.14±5.86、鍼併用群25.47±9.35。②FMA:常軌群25.00±4.78、鍼併用群41.78±7.36。③BI:常軌群30.22±7.74、鍼併用群41.22±9.30。
【連載執筆者】
谷田伸治(たにた・のぶはる)
医療ジャーナリスト、中医学ウォッチャー
鍼灸師
早稲田鍼灸専門学校(現人間総合科学大学鍼灸医療専門学校)を卒業後、株式会社緑書房に入社し、『東洋医学』編集部で勤務。その後、フリージャーナリストとなり、『マニピュレーション』(手技療法国際情報誌、エンタプライズ社)や『JAMA(米国医師会雑誌)日本版』(毎日新聞社)などの編集に関わる。
Q&A『上田がお答えいたします』 丸山議員の質問主意書で分かったこと

Q&A『上田がお答えいたします』 丸山議員の質問主意書で分かったこと
2020.05.10
Q.
丸山穂高衆院議員が提出した『柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問主意書』に対する政府の答弁書を読んだのですが、難しくてよく分かりません。
A.
令和2年3月13日提出の質問主意書ですね。保険者や柔整審査会からの「施術録(カルテ)のコピーを療養費支給申請書に添付してください」との返戻に対する、「なぜ施術録のコピーを付けなければならないのか」との疑義からこのような質問主意書の提出に発展したものと推察できます。 (さらに…)