連載『織田聡の日本型統合医療“考”』148 栗の季節
2020.10.09
栗の美味しい季節になりました。栗きんとんや栗ご飯、もう召し上がられたででしょうか。今回は少し趣向を変えて、「食べ物」のお話を。
日本で栽培される栗は野山に自生する柴栗を原種に、ヤツブサグリやタンバグリなど大粒で甘い実をつけるように品種改良されてきています。栗のスイーツといえば、栗きんとん。私は岐阜出身なので、中津川の栗きんとんに子どもの頃から親しみがあります。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』148 栗の季節

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』148 栗の季節
2020.10.09
栗の美味しい季節になりました。栗きんとんや栗ご飯、もう召し上がられたででしょうか。今回は少し趣向を変えて、「食べ物」のお話を。
日本で栽培される栗は野山に自生する柴栗を原種に、ヤツブサグリやタンバグリなど大粒で甘い実をつけるように品種改良されてきています。栗のスイーツといえば、栗きんとん。私は岐阜出身なので、中津川の栗きんとんに子どもの頃から親しみがあります。 (さらに…)
連載『中国医学情報』187 谷田伸治

連載『中国医学情報』187 谷田伸治
2020.10.09
☆新型コロナウイルス肺炎回復期中医リハビリ推奨ガイドライン(国家試行版)―鍼灸関連部分
武漢の李暁東(湖北省中医院)らは、COVID-19による肺炎(中文:新型冠状病毒肺炎、以下「新冠肺炎」と略記)の回復期患者に対する、国家衛生委員会辦公庁・国家中医薬管理局の「新冠肺炎回復期中医康復指導建議(試行)」(2020年2月22日)を解説した。以下、その鍼灸関連の治療法を紹介する(中医雑誌、20年11期)。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 PTA連合会の給付から柔整施術を締め出すのは柔整師退場へのプロセスだ

Q&A『上田がお答えいたします』 PTA連合会の給付から柔整施術を締め出すのは柔整師退場へのプロセスだ
2020.10.09
Q.
岩手県PTA連合会が共済金の支払いにおいて「柔道整復師の外傷に係る施術について先行して医師の治療を要件とすること」としていますが、これに納得がいきません。
A.
おっしゃる通り、一般社団法人岩手県PTA連合会は2020年度の共済事業の実施に当たり、令和2年4月1日以降に発生した外傷性の負傷で柔整施術を受療した場合における共済金の支払いについて、医師による療養の給付を必須条件としています。こんなことを許してはなりません。私も早速、同連合会へ疑義を申し立て、議論している最中です。柔整師は医師から独立して自らの見立てをもって、急性の外傷の治療としての施術を行う資格を厚生労働大臣から免許を受けているのです。 (さらに…)
連載『汗とウンコとオシッコと…』194 Mixed 3 season

連載『汗とウンコとオシッコと…』194 Mixed 3 season
2020.10.09
赤い糸をまき散らすように、彼岸花が時計で計ったかのごとく咲きだした。と思えばまだ日中に蝉の声が聞こえる。秋と夏が挾雑するややこしい季節だ。脉がこれに従って、夏と秋が混じる人、秋を春と勘違いした人に大きく分けられて面白い。夏と秋が混在すると身体が感じれば寸関尺の長さが短くなり、浮大を呈する。病症は内熱状態になり、腹満して体幹部に病が出やすく腰痛を呈しやすく、関節の腫脹や下肢痛に浮腫を伴う症状を訴える。一方、身体が秋を春と勘違いした場合は脉が浮濡長となり、上焦部に病が現れ頭痛や筋の引き攣り、ぎっくり腰様の症状を現すことが多い。
森畑の友人の高校教師、服部が顧問を務める陸上部に所属する少年、新田くんが来院した。 (さらに…)
連載『医療再考』20 医療を再考する―医療を飲み込むIT化の波
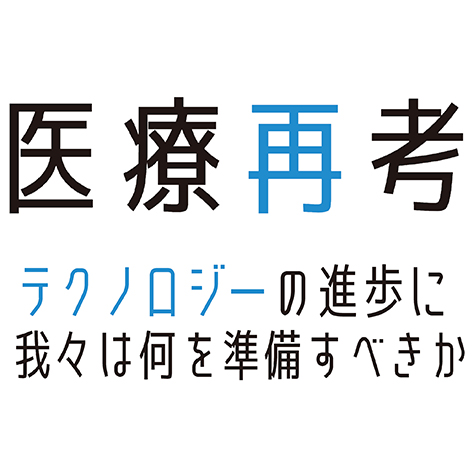
連載『医療再考』20 医療を再考する―医療を飲み込むIT化の波
2020.10.09
第4次産業革命と呼ばれるIT革命を受け、医療はその中心をオンラインへ移行し始めています。最大のIT革命は医療情報である電子カルテの普及です。今まで病院ごとに保管されていた紙ベースの情報が、電子カルテ化によって多くの似たような情報を集積することが可能となりました。集めたデータを内容ごとに集約したビッグデータを解析することで新たな知見が生まれ、エビデンスとして認められるようになってきました。 (さらに…)
今日の一冊 カメの甲羅はあばら骨 人体で表す動物図鑑

今日の一冊 カメの甲羅はあばら骨 人体で表す動物図鑑
2020.10.09
カメの甲羅はあばら骨 人体で表す動物図鑑
川崎悟司 著
SBビジュアル新書 1,100円
亀の甲羅は人体における肋骨に相当する。ヒトの肋骨を巨大化させて肩甲骨と骨盤を包み込むと、「カメ人間」の出来上がり。背中と頭部に「皮骨」を生じさせれば「アルマジロ人間」に。鎖骨を前方に出し、胸筋を異常に発達させれば「トリ人間」。人間の体を爬虫類や哺乳類、鳥類など、23の動物の体の一部に変形させたイラストで表現し、その構造を分かりやすく解説。またそれらの構造にはどんな機能があるのか、さらに太古の地球の生物が環境にどのように適応し、姿を変えてきたのかの秘密にも迫る。
『医療は国民のために』303 施術管理者研修の収益を保険者との信頼構築のために使っては?

『医療は国民のために』303 施術管理者研修の収益を保険者との信頼構築のために使っては?
2020.09.25
9月よりあはき療養費の受領委任でも施術管理者研修の申し込みがスタートするなど、柔整同様の適正化方策が着実に進捗している。同研修は、あはきが東洋療法研修試験財団、柔整が柔道整復研修試験財団と、ともに公益財団法人が「研修実施機関」となり、研修を主催している。 (さらに…)
連載『先人に学ぶ柔道整復』二十三 二宮彦可(前編)

連載『先人に学ぶ柔道整復』二十三 二宮彦可(前編)
2020.09.25
多くの師匠に学び『正骨範』を完成
今回から、現存する江戸期の接骨術の古典として有名な『正骨範』を著わした、二宮彦可(にのみやげんか、1754―1827)を取り上げていきます。彦可は、前回の本連載で紹介した吉雄耕牛から多くを学んだとの記録が残っています。しかし、耕牛以外にも師匠と呼べる人物がたくさん存在していたという彦可の生い立ちを概観します。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』147 コロナ禍で発熱しないためにできること

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』147 コロナ禍で発熱しないためにできること
2020.09.25
私のクリニックでは、インフルエンザのワクチン接種への問い合わせが増えてきました。コロナ禍で多くの人が感染症対策を講じていたためか、昨シーズンのインフルエンザの流行レベルは、定点受診者数のピークで見ても、過去2年間と比較しても、50%にとどまりました。今シーズンもおそらく流行はかなり抑えられるのではないでしょうか。 (さらに…)
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』186 「母趾種子骨障害」と誤診された足底部嚢腫症例報告

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』186 「母趾種子骨障害」と誤診された足底部嚢腫症例報告
2020.09.25
小野博道(筋・骨格画像研究会)
患者は36歳男性(会社員)で、体格は痩せ型。主訴は左母趾球の痛みで来院時の体温は36.6℃。2週間前より、毎朝の日課であるランニング中、左母趾球に違和感があった。ランニング以外の私生活でも日に日に痛みが増してきたため、いつも通っている治療院を1週間前に受診。その治療院では、過多なランニングによる「母趾種子骨障害」と評価され、温熱療法・マッサージ・テーピング処置が施された。その後も3日間通い同処置を施し様子を見ていたが、歩くこともできなくなるほどに痛みが増強したため不安に感じ、当院を受診した。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 コロナの慰労金は、あはき・柔整には出ない?

Q&A『上田がお答えいたします』 コロナの慰労金は、あはき・柔整には出ない?
2020.09.25
Q.
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」は医療機関の医療従事者や職員を対象にしていますが、これに、あはき治療院、接骨院は含まれないのでしょうか。
A.
ご質問にある慰労金ですが、①感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴い、②継続して提供が必要なサービスであること、③医療機関でのクラスターの発生状況、の3点を踏まえ、医療機関等に勤務し、患者・利用者と接する者を支給の対象としています。すなわち、 (さらに…)
連載『食養生の物語』88 生命に不可欠な塩

連載『食養生の物語』88 生命に不可欠な塩
2020.09.25
「敵に塩を送る」とは、戦国時代に上杉謙信が敵対関係にあった武田信玄に塩を送って苦境から救った逸話に由来する言葉。塩が活力の源であることの表れでもあります。英語で塩はsalt。給料を意味するsalaryと共にラテン語のsal(塩)に由来します。日本でも平安時代の官吏の給料が塩で支払われていたそうです。塩は生きていく上で不可欠なものと考えられてきたのですね。陰陽五行で生命力を主る「腎」を養うのは「鹹」、塩のこと。塩分が過不足なく補われることが大切だと考えられています。生命は、30億年前に海の中で誕生したもの。私たちの細胞レベルで、細胞外液が海水とよく似た成分で満たされているのはその名残と考えられますし、アトピー性皮膚炎の人が海水浴に行くことで改善するといわれるのも納得いきます。 (さらに…)
連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』23 かならずめぐる四季

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』23 かならずめぐる四季
2020.09.25
今年の夏は日中の気温が高かったのと、マスクを着ける習慣が加わって、暑くて大変でしたね。けれど、決して天は間違わないので、今年もちゃんと陽気の力は正しい時期に徐々に弱まり秋になりました。 (さらに…)
今日の一冊 認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由

今日の一冊 認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由
2020.09.25
認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由
木之下 徹 著
講談社+α新書 880円
著者は、日本初の認知症専門の訪問診療を始め、現在は認知症外来の専門医。数千人の認知症患者と接してきたという経験を基に、認知症にまつわる多くの誤解を切る。「認知症に病識はない」は真っ赤な嘘。「認知症予防」に有効な方法は何もない、必要なのはなった時の準備。そもそも、認知症を「頑張れば進行しないもの」と考えてはいけない――。なぜ患者は同じ言葉を繰り返すのか、認知症患者に寄り添い続けてきた著者だからこそ推し測れる本音を通じて、本人も周囲も納得できる生き方を考える。
『医療は国民のために』302 柔整・あはき業界も「マイナポータル参入」を考えてみては

『医療は国民のために』302 柔整・あはき業界も「マイナポータル参入」を考えてみては
2020.09.10
厚労省の柔整療養費検討専門委員会で、「電子請求」の議題が持ち上がって久しい。数年以上も議論を続けているが、実質何も進んでいないのは明らかで、いまだにモデル事業の実施に向けた準備を話し合っている状況だ。いつまで「ルール作り」に時間をかけるのか、不思議でならない。少なくとも、電子請求が「オンライン請求」のことを指しているのか、といった程度は明言してもらいたい。仮に、オンライン請求であるとすれば、内閣府が推し進めている「マイナポータル」への参入を議論しなればならないからだ。 (さらに…)
連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』29 レーザーリプロ学会

連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』29 レーザーリプロ学会
2020.09.10
3月に予定され延期となった日本レーザーリプロダクション学会が、8月23日にヒルトン大阪で開催されました。講演を依頼されていた私は録画によるビデオ講演も打診されていたのですが、学会への出席は色んな方々との交流も大切な目的なので、そのまま参加することにしました。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』146 コロナ禍の医療サービスは患者目線で

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』146 コロナ禍の医療サービスは患者目線で
2020.09.10
コロナの影響で、医科や歯科の診療報酬もそうですが、柔整・あはき療養費の請求件数も大きく減少していると聞いています。特に第1波の頃、受診したくても外出を控えて、じっと自宅で痛みなどを我慢している患者も多く、適切な医療・施術を受けられない場合がありました。病院でも手術がストップしていたという話はよく聞かれました。 (さらに…)
連載『中国医学情報』186 谷田伸治

連載『中国医学情報』186 谷田伸治
2020.09.10
☆新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療例―バイブレーション治療器併用68例
武漢の黄海(湖北省中医院)らは、COVID-19による肺炎(中文:新型冠状病毒肺炎、以下「新冠肺炎」と略記)患者で、現代医学の常軌の治療法にバイブレーション治療器を併用し、臨床症状の改善などを認めたと発表(鍼灸臨床雑誌、20年5期)。
対象=入院中の新冠肺炎(普通型)68例(男29例・女39例)、年齢33~84(平均60.68±13.98)歳。
※「軽型」:症状軽微、肺炎の画像所見なし。「普通型」:発熱・呼吸器症状などと肺炎の画像所見あり。「重型」:呼吸回数が30回/分以下、血中酸素濃度測定SpO2が93%以下、動脈血酸素分圧/吸入酸素濃度が300mmHg以上、これら3項中1項該当。―国家衛生健康委「新冠肺炎診療方案(試行第六版)」
治療法=<治療器>上海生生医用器材有限公司(米国Body Rub Incの子会社)の「按摩器SSA-600型」(ネットで画像閲覧可)。
<操作法>施術者は、マスク・防護眼鏡・フェイスシールドなど装着。患者は座位か伏臥位。術者は患者の背部で、治療器を両手で保持し、下(第2腰椎の命門・腎兪のライン)から上(第7頸椎棘突起下の大椎)まで、移動路線(気管支の分布に一致)に沿って外から内に、先に右半身その後左半身で移動。その持続振動時間は約2.5分間。次に患者の前方の胸骨部を0.5分間。振動回数は毎分2,800回。毎回合計約3分間、毎日1回を退院まで。
観察指標=①ウイルスのPCR検査(治療器使用前・終了後)、②12の臨床症状―発熱・乾咳・倦怠感(乏力)・胸部不快感(胸悶)・息切れ(気短)・食事量減少(納差)・咽痛/痒・咳白色痰/黄色痰・発汗・下痢・鼻閉・頭痛/めまい、③バーセルインデックス(Barthel Index):食事・移乗・整容・トイレ動作・入浴・移動・階段昇降・更衣・排便自制・排尿自制10項目を評価、④6分間歩行試験(6MWT)、⑤「重型」などへの転化率
結果=平均入院日数18.18±7.06日。①治療前検査者30例:陽性16例・陰性14例→治療後の陽性23例(陰性→陽性12例)・陰性7例(陽性→陰性5例)(無変化13例)、陽性検出率は治療前より高いが、統計学的有意差なし。②食事量減少・発汗は、治療前後の有意差なし。他の10症状は、有意に改善。③・④ともに有意に改善。⑤悪化者なし。
<付記>新冠肺炎の鍼灸治療例は本欄2020年8月10日号で紹介。
☆中・重度の癌性疼痛60例で医療用麻薬単独と鍼併用治療とをランダム化比較
安徽中医薬大学・李丹らは、中・重度の癌性疼痛にはオピオイド鎮痛薬単独より鍼併用治療が有用と報告(中国鍼灸、20年3期)。
対象=60例(男36例・女24例、30~80歳)。これをランダムに単独群・鍼併用群各30例に分けた。内訳―単独群:平均58±11歳、肺癌8例・胃癌9例・肝癌7例・大腸癌6例、中等度疼痛19例・重度疼痛11例。併用群:平均55±12歳、肺癌9例・胃癌7例・肝癌8例・大腸癌6例、中等度疼痛21例・重度疼痛9例。両群に有意差なし。
治療法=両群とも連続2週間治療。オキシコドン塩酸塩(oxycodone hydrochloride)徐放錠を服用。
<鍼治療>①主穴―合谷・内関・足三里・三陰交。②配穴(原発臓腑と疼痛部位で弁病取穴・循経取穴)―背兪穴・郄穴・阿是穴など。[例]肺癌:肺兪・阿是穴、めまい:百会・風池、悪心嘔吐:胃兪・脾兪・足三里、便秘:天枢・大腸兪、尿閉:中極・膀胱兪。③操作―0.25mm×25mm、0.30mm×40mmのディスポ鍼使用。合谷・内関は直刺13~20mm、足三里・三陰交は直刺25~30mm、平補平瀉法。配穴は病状による。置鍼30分間(この間に行鍼1回)。毎日1回治療。
観察指標=①毎日の服用量、②有害事象、③カルノフスキーの一般全身状態スコア(KPS)ほか
結果=単独群:完全緩解11例・部分緩解12例・軽度緩解5例・無緩解2例・緩解率(完全+部分)76.7%、併用群:完全緩解13例・部分緩解14例・軽度緩解2例・無緩解1例・緩解率90.0%。
①(前→後/mg)単独群:92.00±64.46→108.67±59.98、併用群:94.67±65.58→64.33±47.76。②単独群:便秘13例・悪心嘔吐8例・めまい5例・尿閉2例、併用群:便秘6例・悪心嘔吐4例・めまい3例・尿閉1例。③(前→後)単独群:63.67±10.33→71.67±9.86、併用群:64.00±9.32→78.33±8.33。
【連載執筆者】
谷田伸治(たにた・のぶはる)
医療ジャーナリスト、中医学ウォッチャー
鍼灸師
早稲田鍼灸専門学校(現人間総合科学大学鍼灸医療専門学校)を卒業後、株式会社緑書房に入社し、『東洋医学』編集部で勤務。その後、フリージャーナリストとなり、『マニピュレーション』(手技療法国際情報誌、エンタプライズ社)や『JAMA(米国医師会雑誌)日本版』(毎日新聞社)などの編集に関わる。
Q&A『上田がお答えいたします』 あはきの施術管理者研修の 受講者募集がようやく開始

Q&A『上田がお答えいたします』 あはきの施術管理者研修の 受講者募集がようやく開始
2020.09.10
Q.
あはき受領委任の施術管理者研修の受講者の募集が始まったとのことですが、柔整のように不手際で受講希望者が満足に研修を受けられないなどということにはならないでしょうか。
A.
令和2年8月6日付で、あはき療養費の受領委任の施術管理者研修の実施機関として公益財団法人東洋療法研修試験財団が登録され、令和3年1月~3月実施分について、9月1日から財団のホームページ上で募集を開始しました。今後、研修の実施に向けた通知や事務連絡等が厚労省及び財団から発出されますので、適宜確認の上その指示に従って申し込み、受講していくことになります。 (さらに…)
連載『汗とウンコとオシッコと…』193 集まる

連載『汗とウンコとオシッコと…』193 集まる
2020.09.10
9月に入ったというのに、日中は30度を超え体温に近づく、残暑ならぬ残酷暑が続く。こうなると身体は脱水予防の防衛反応で発汗を減じ、尿も出さなくなる。すると口渇がさらに強まり、水をがぶ飲みして血圧が上がり熱中症に至る負のスパイラルにはまり込んでしまう。コロナウイルス対策のマスクが頭に熱をこめてこれを助長するのも難しいところだ。昔の日本人が経口補水液の代わりにハト麦茶、いわゆる薏苡仁のお茶に塩を入れて電解質を調整し、口渇を抑え脱水予防していた知恵には本当に頭が下がる。戦後改革で表に出なくなった古来の踏襲も見直されるべきではないか。 (さらに…)