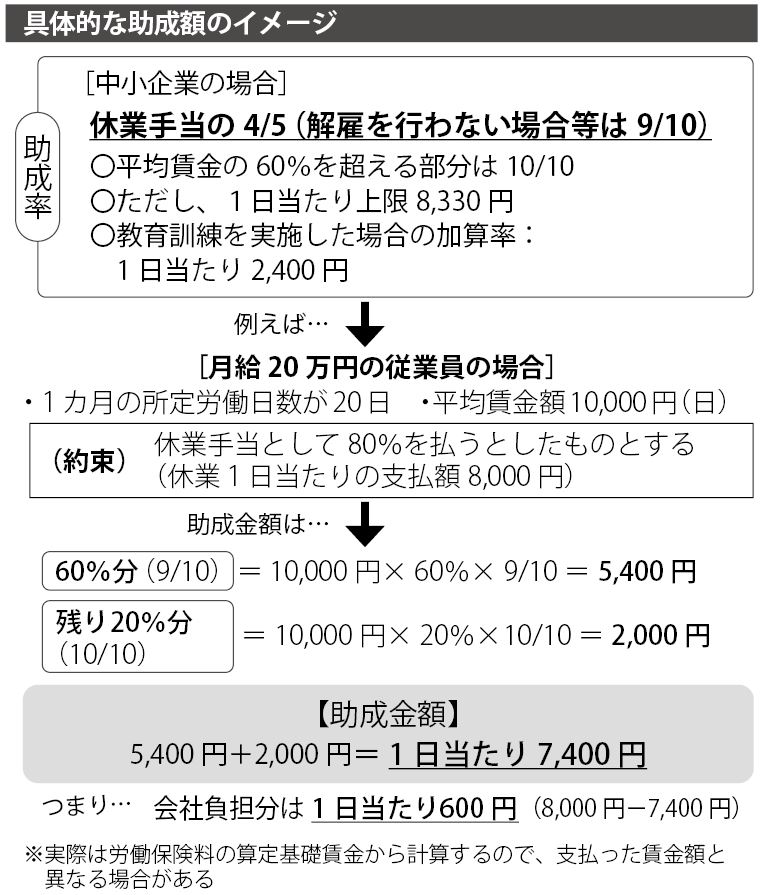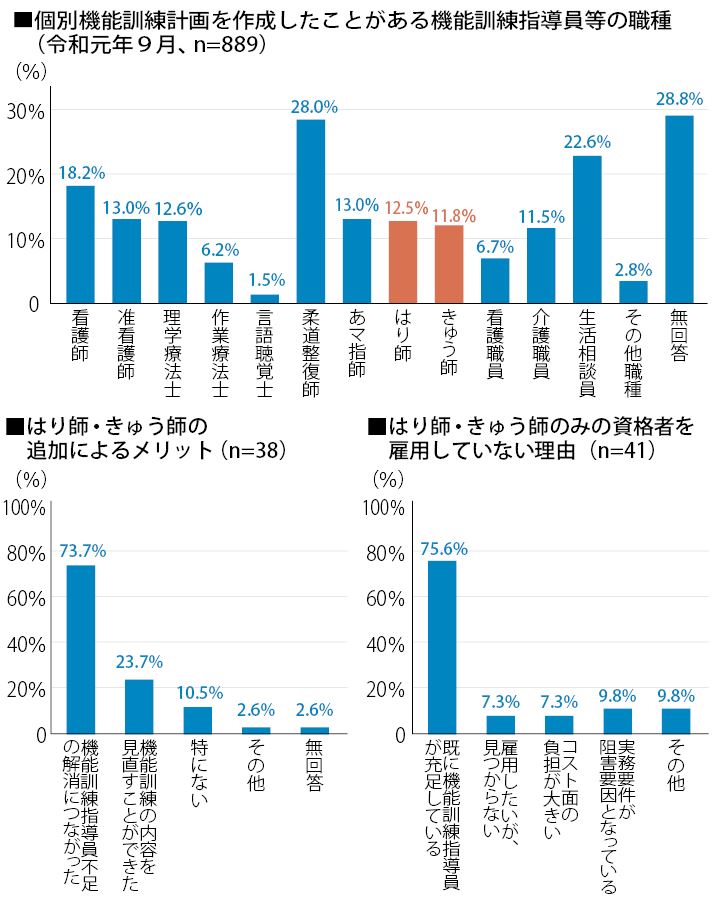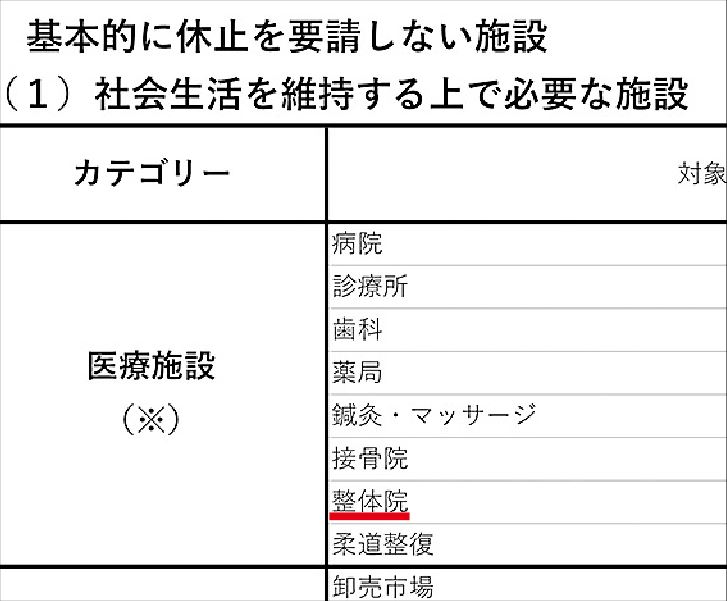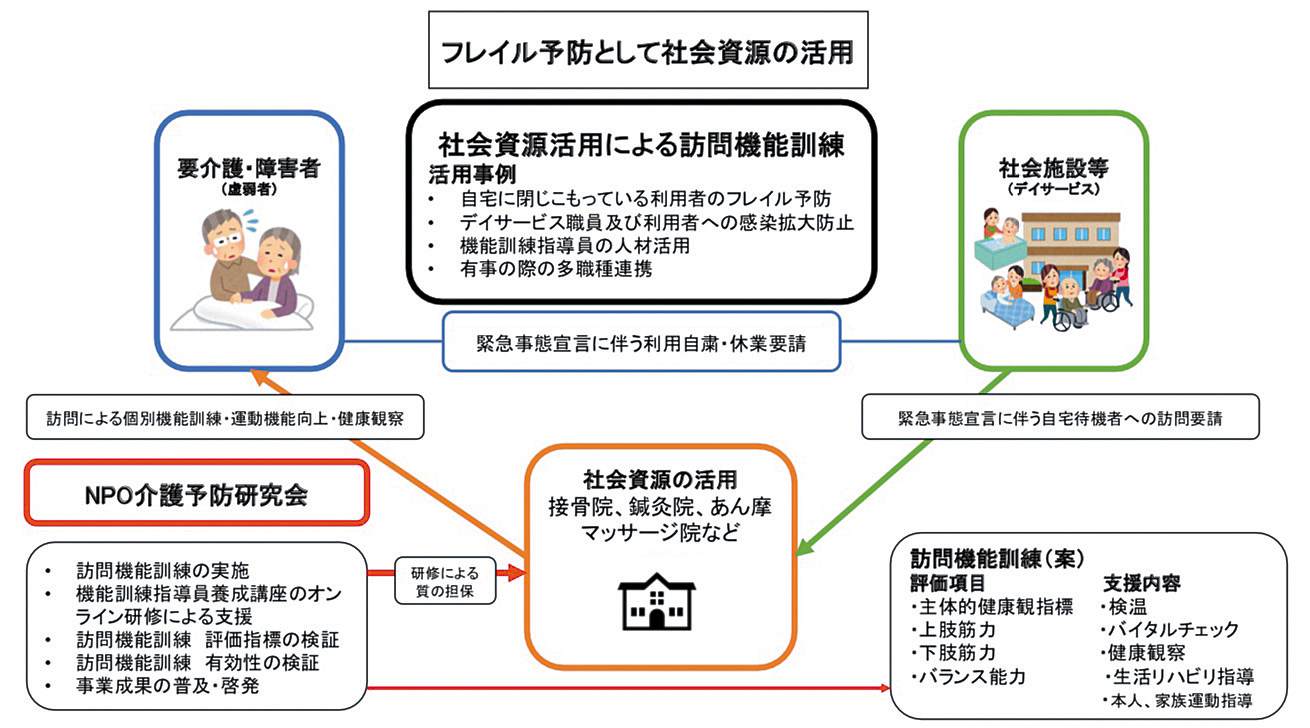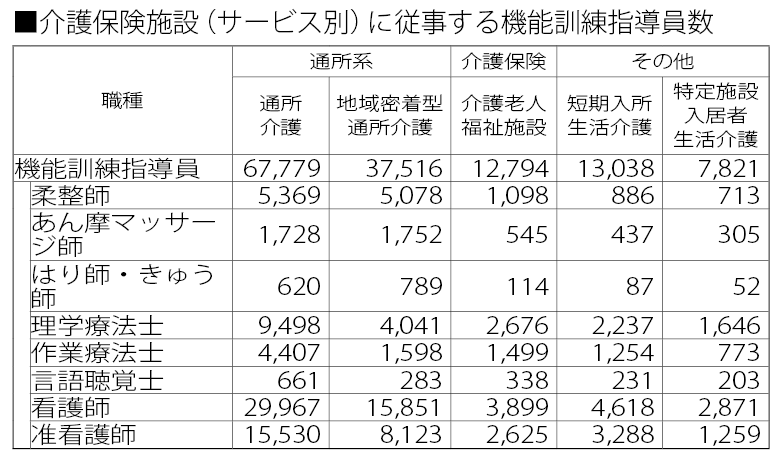フレアス、同業他社の子会社化で拠点大幅拡大
2020.06.03
全国で在宅マッサージと訪問看護・介護の事業所を展開している株式会社フレアス(澤登拓代表取締役社長)が6月1日、訪問マッサージのフランチャイズ事業を行う株式会社オルテンシアハーモニーの株式を取得し、子会社化した。これによりフレアスの事業所数は直営店で85から86に、フランチャイズで31から196になり、合計は116から282拠点となった。
なお、オルテンシアハーモニーは株式会社レイスヘルスケアが事業の一部を分割して新たに設立した会社。
フレアスHP