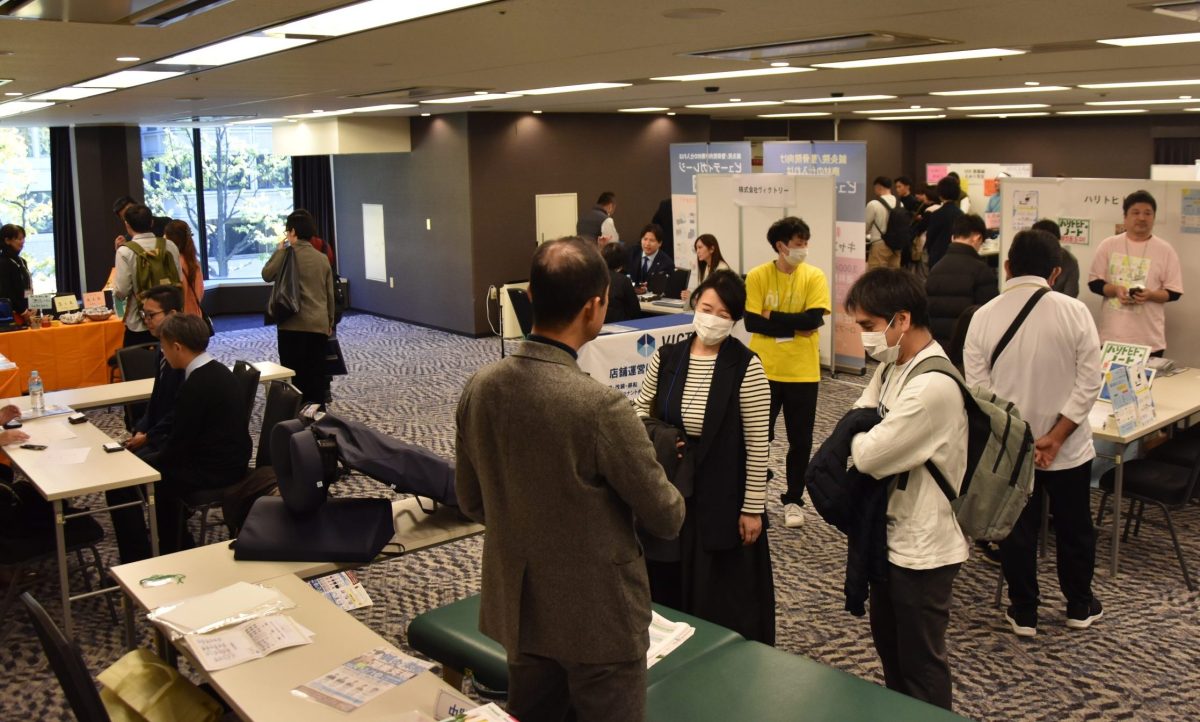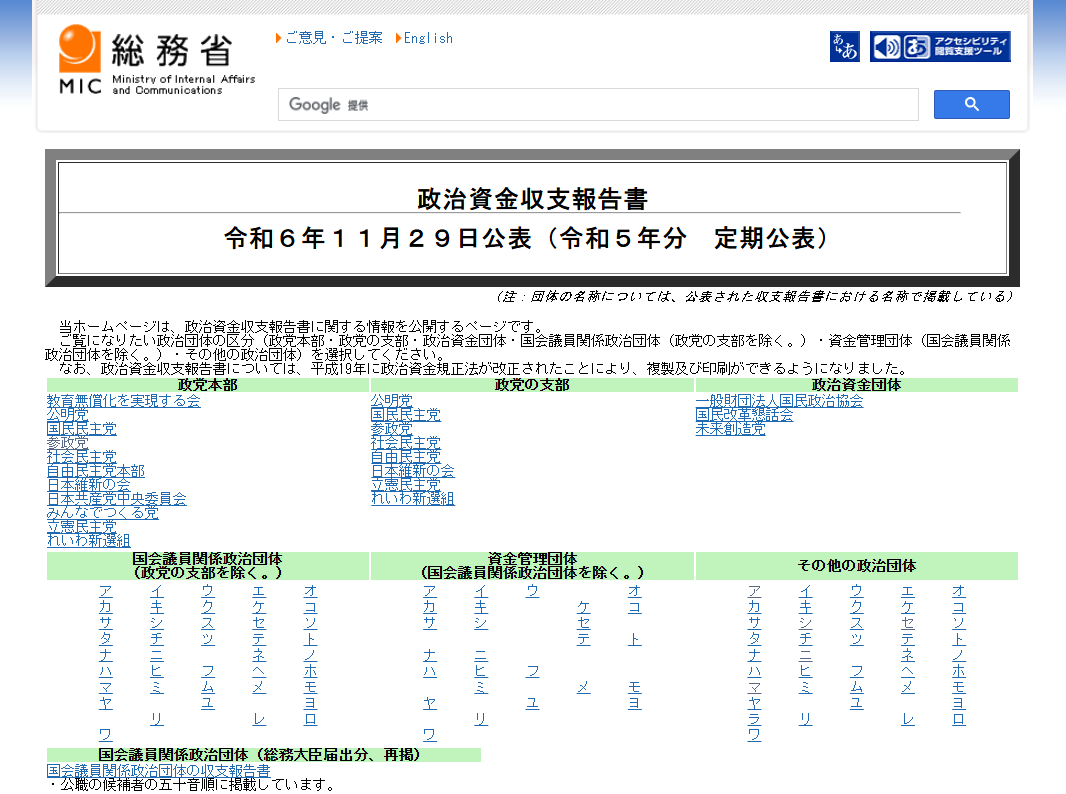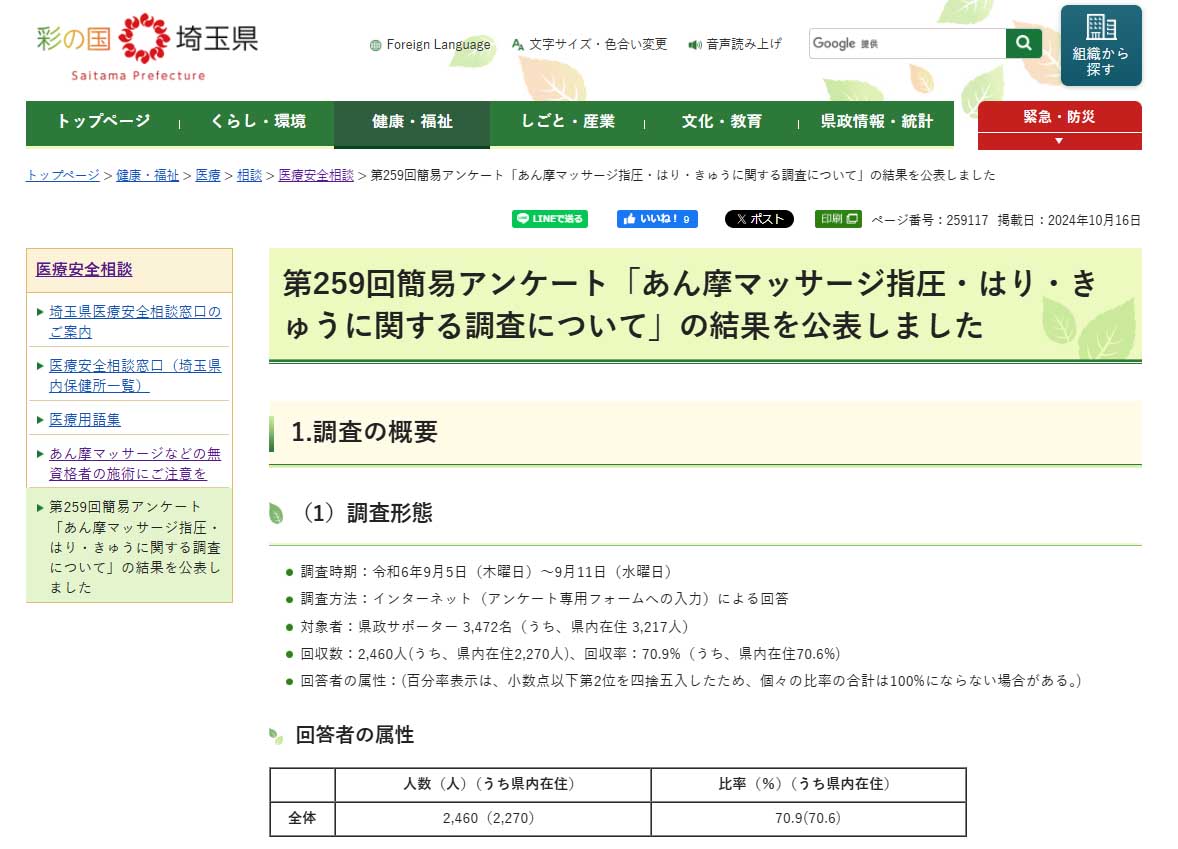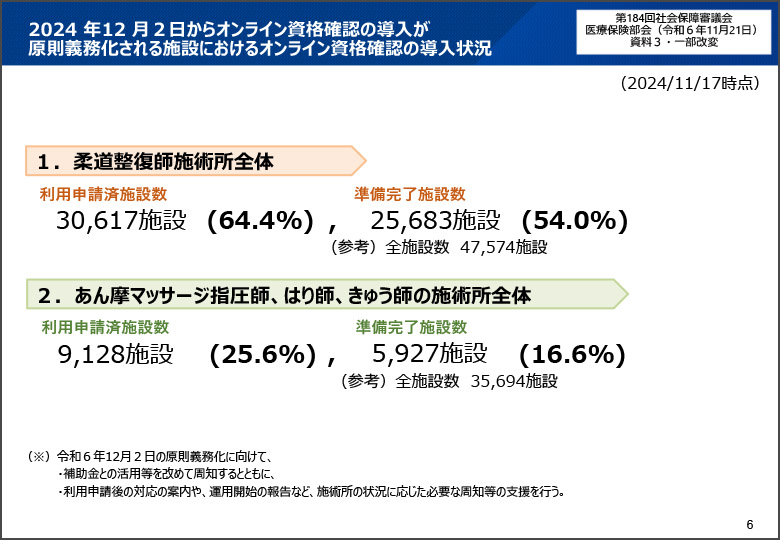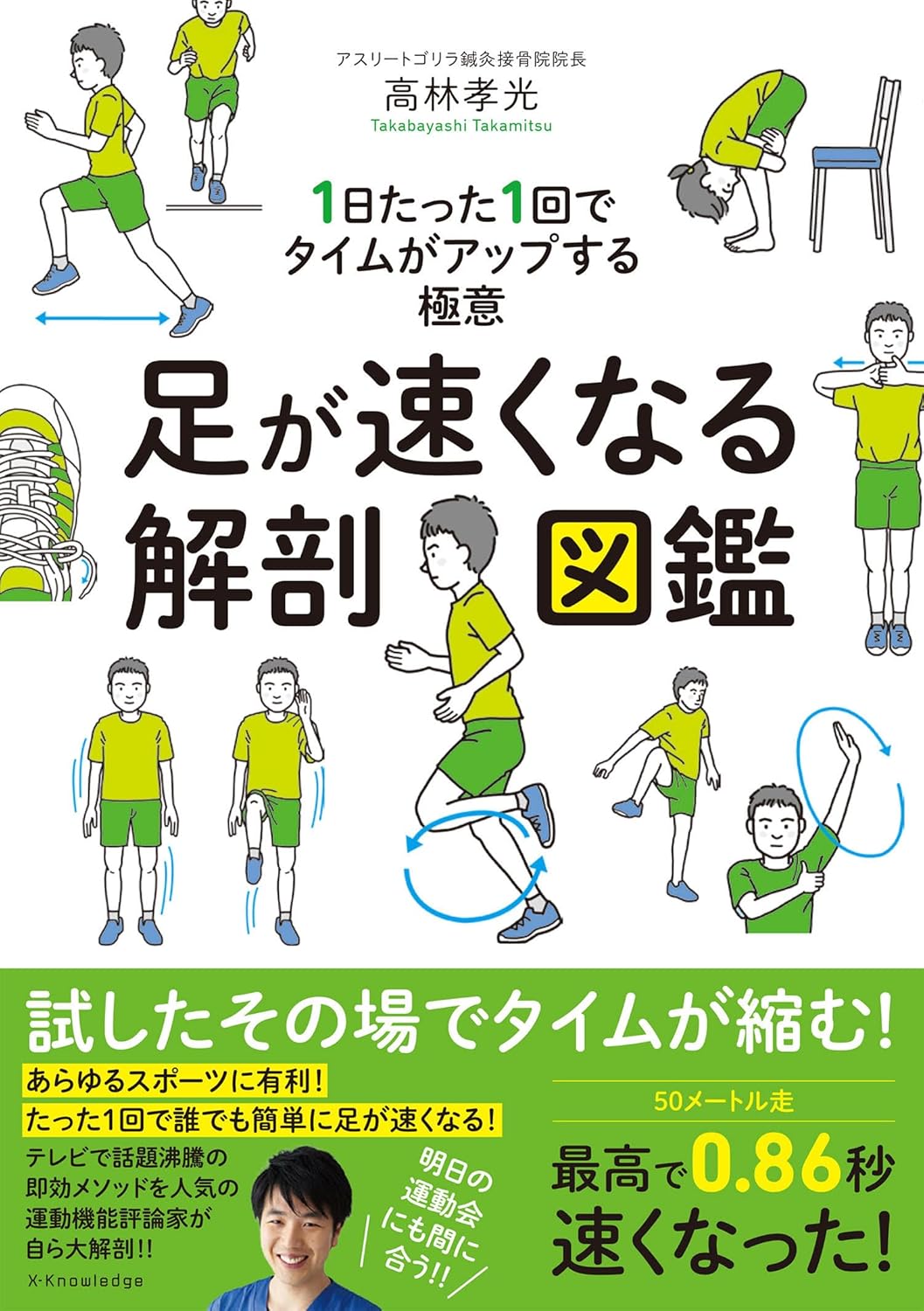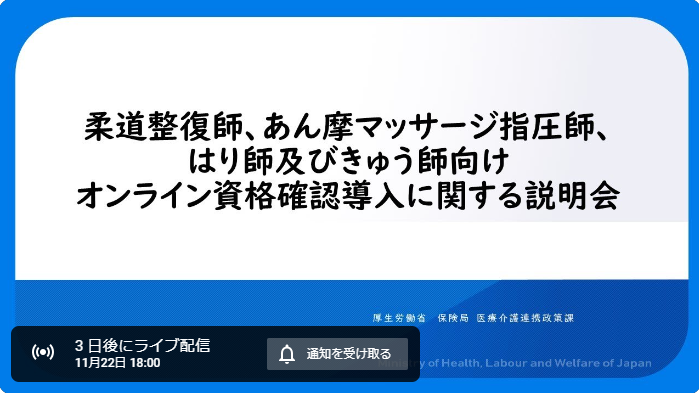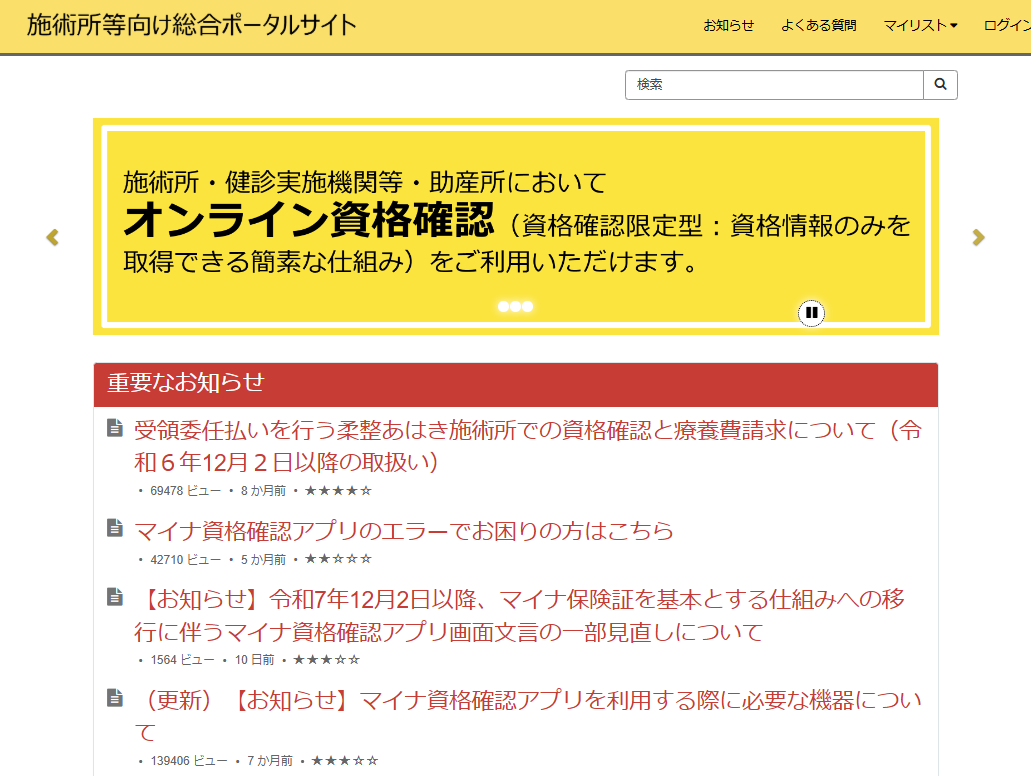連載『汗とウンコとオシッコと…』244 賊風
2024.12.10
12月に入ってようやく寒くなり一気に紅葉が始まった。だが、日中は15度以上もあり、初めてモミジの紅葉と皐月・シャクナゲの開花を同時に見た。こんな気候は身体に実に堪える。こうなるとまず、衛気の発散が狂い血圧のコントロールが難しくなる。体幹血圧が上昇し、夕方急に眠くなったり、頭痛や眩暈、耳鳴がしたり、逆に朝に起きられず夕方から楽になるケースもある。上焦だけの回転が上がり身熱症状と膈下の厥冷症状が現れ、いわゆる木象と火象が冬になって暴れてしまう上熱下冷虚となるわけだ。
「以前にメニエールでお世話になりましたね」 (さらに…)