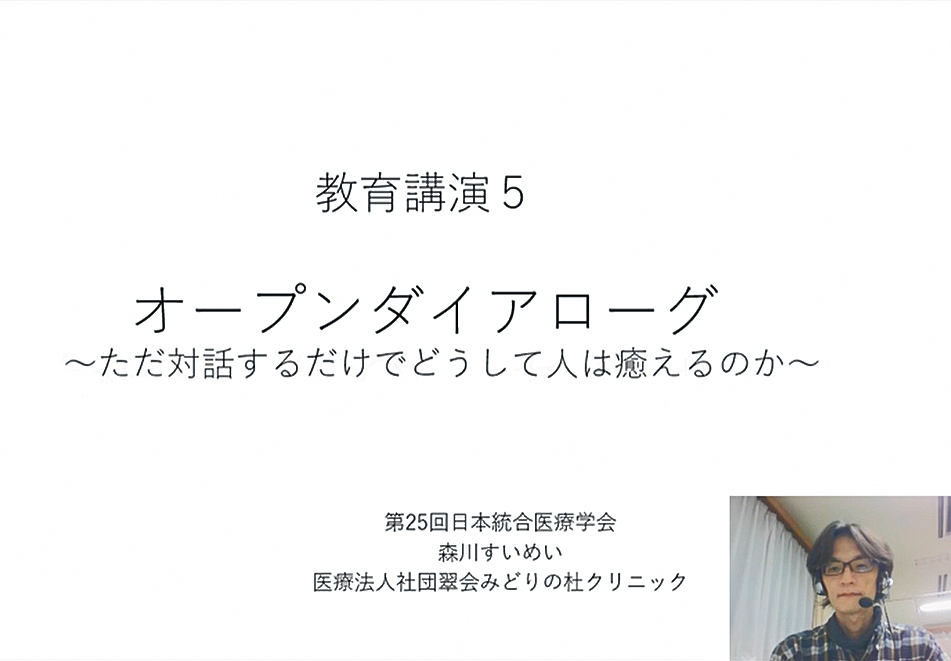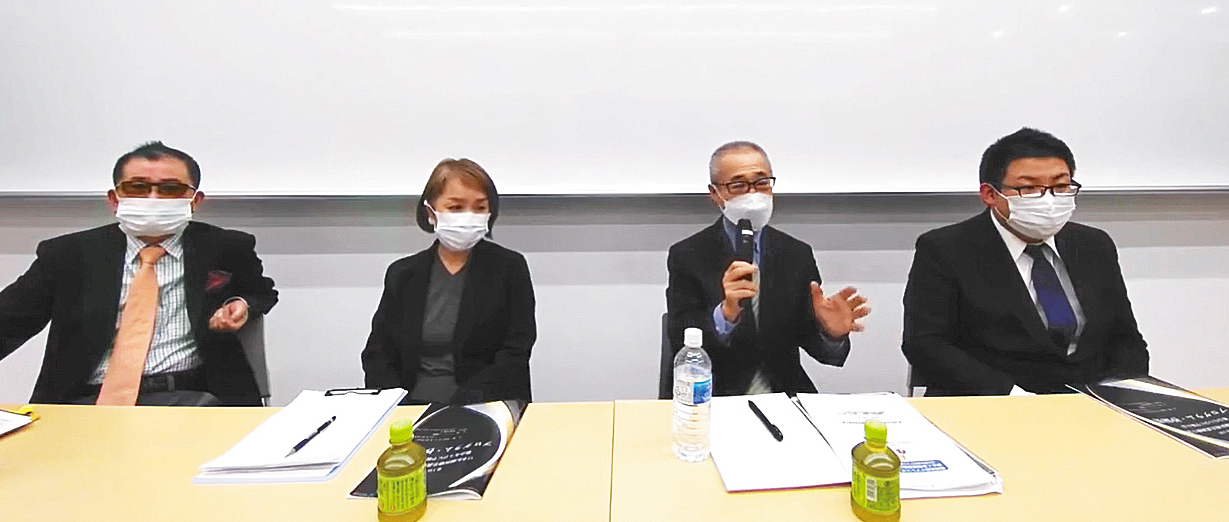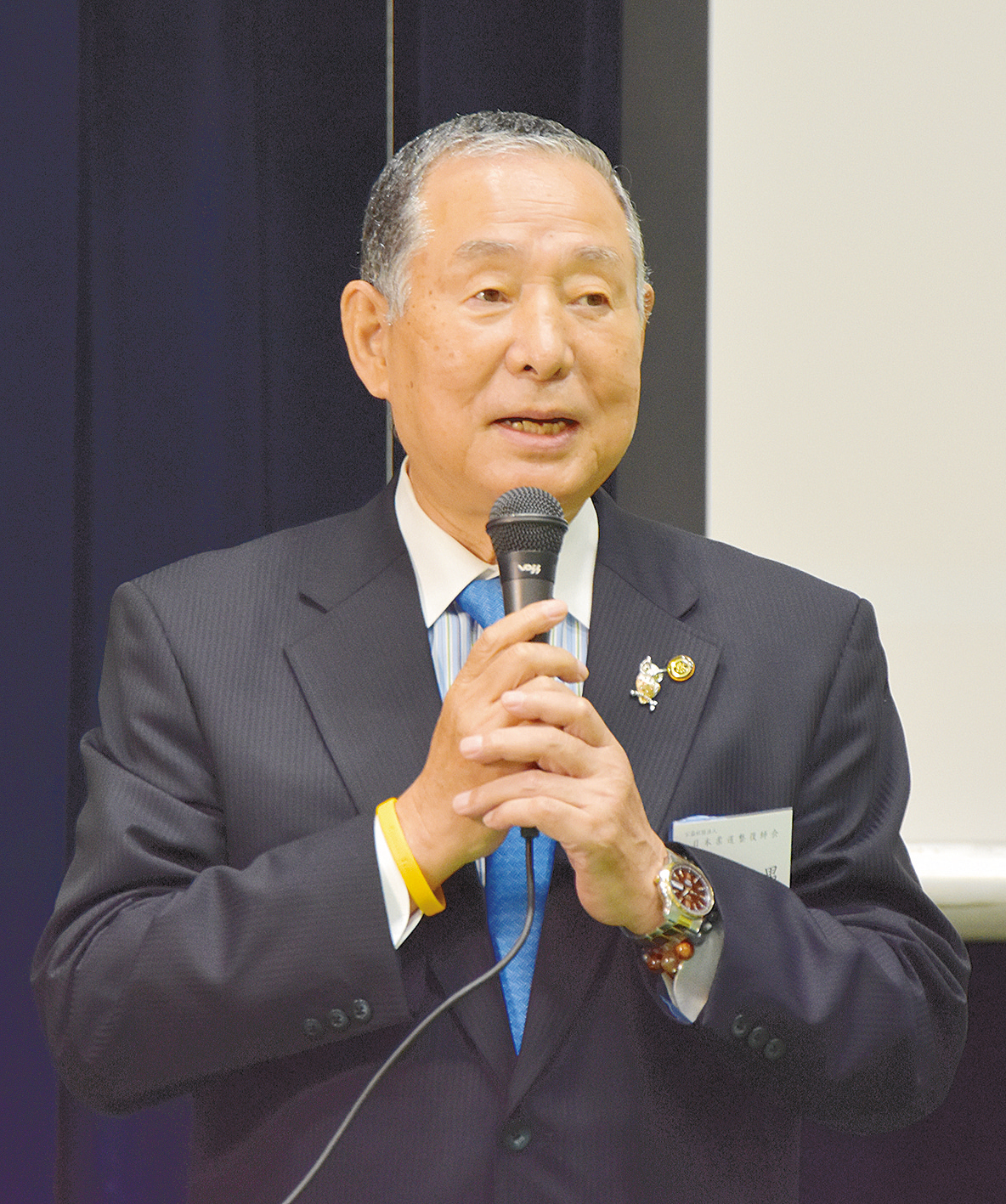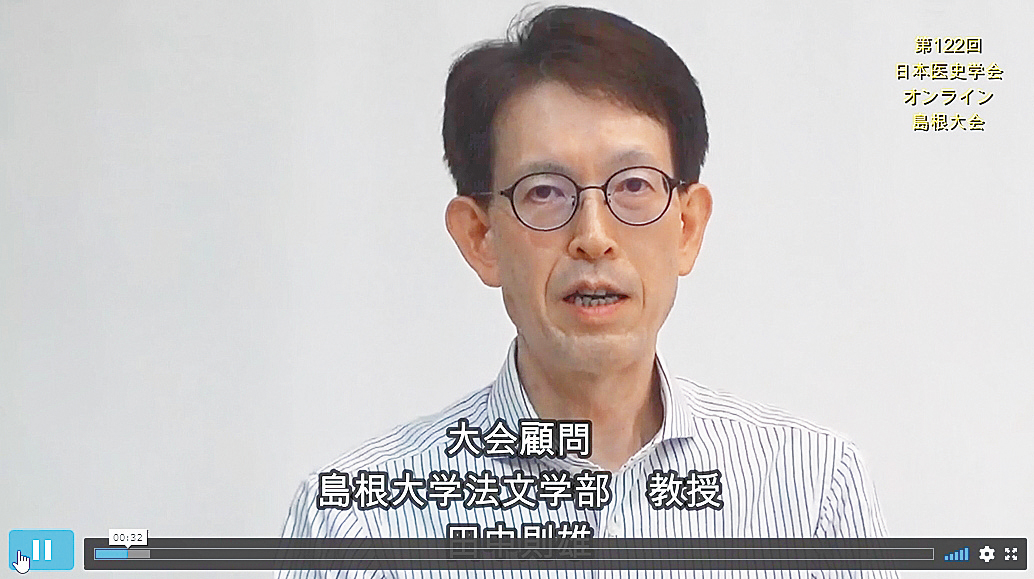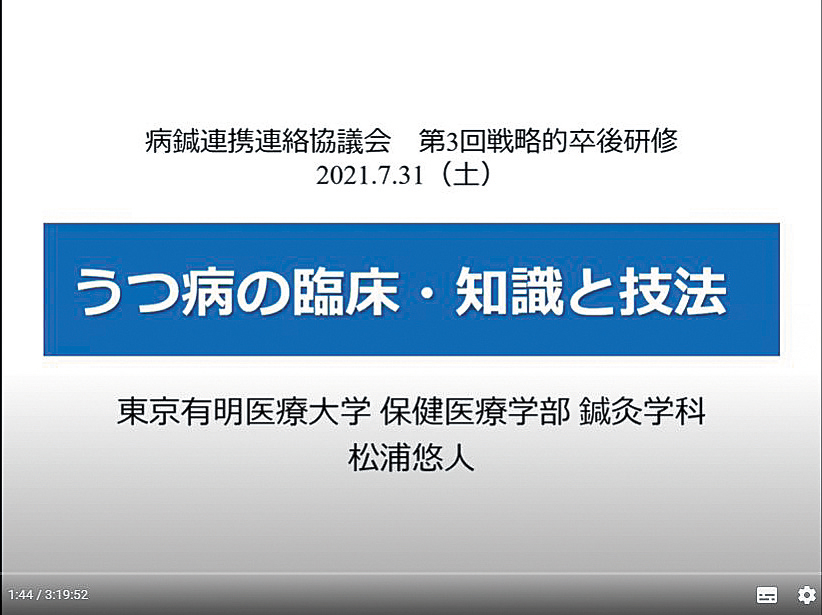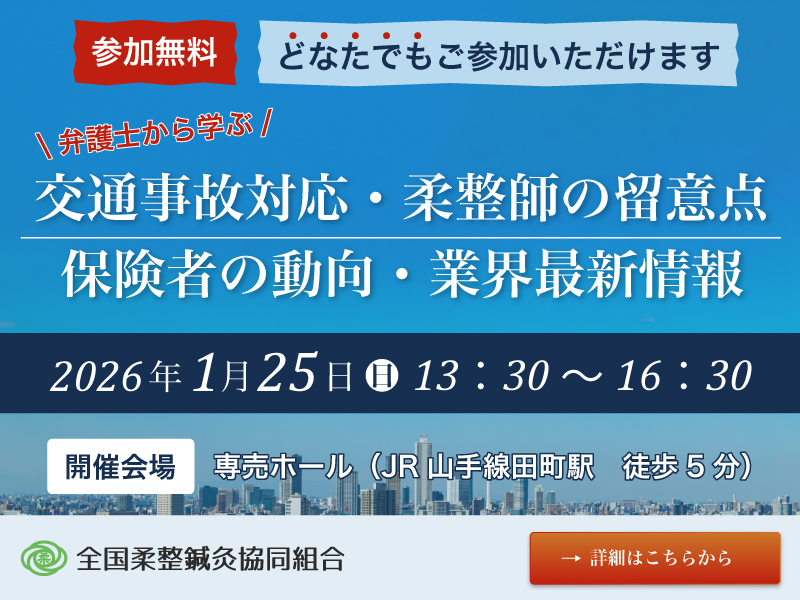第43回日本疼痛学会 痛みに対する鍼治療でシンポ
2022.02.25
薬物無効の難治例に改善示唆
昨年12月10日から11日にかけてウェブ開催された第43回日本疼痛学会(富永真琴会長)において、鍼治療に関するシンポジウムが行われた。テーマは『痛みに対する鍼治療の効果とその作用機序』で、全日本鍼灸学会との共催。座長の山口智氏(全日本鍼灸学会副会長)は、「第43回学会の会長を務める富永先生とは以前から灸の作用機序などについて意見を交換し、共同研究を進めたいと話してきた経緯から、こうした機会を頂きました」と共催の経緯を説明した。
皆川陽一氏(帝京平成大学ヒューマンケア学部)は線維筋痛症患者に対する鍼治療について、一般に診断に使用される圧痛点18カ所が経穴の位置と高い確率で一致し、関連性が示唆されるとしたほか、2010年以降5件のメタ解析が報告されるなどエビデンス蓄積が進んでいると説明。 (さらに…)