ブラジルで鍼灸が法制化
2026.02.09
投稿日:2025.11.05
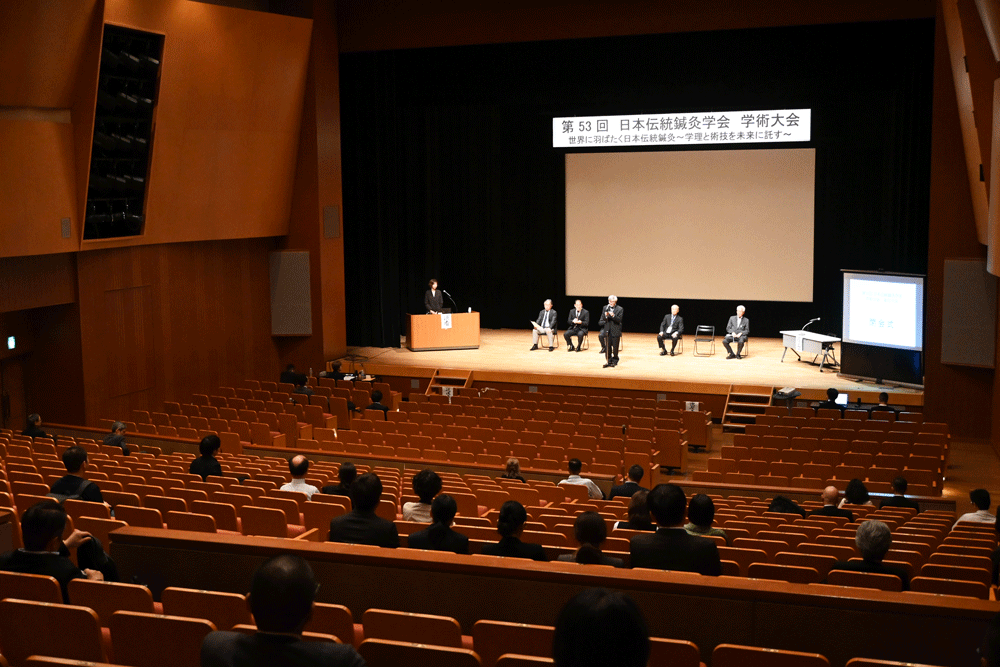
第53回日本伝統鍼灸学会学術大会が10月11日、12日にタワーホール船堀(東京都江戸川区)で開催された。テーマは『世界に羽ばたく日本伝統鍼灸―学理と術技を未来に託す』。約600人が会場に足を運び、アーカイブも合わせ当日までに653人の申し込みがあった。
会頭講演では谷内秀鳳氏(東洋はり医学会会長)が『今日における難経六十九難の治療法則―片方刺しによる相剋調整の本治法』のテーマのもと、同会は経絡治療の流れを継ぐ5名の盲人鍼灸師から始まった学会であると紹介した。現在は国内33支部、海外14支部を構えている。
同会では、2つの証を立て左右に振り分け共に補う「片方刺しによる相剋調整の本治法」や鎖骨上窩に対する「ナソ治療」、鼡径部に対する「ムノ治療」という標治法を打ち出し実践しているという。治療の流れとし、主訴、望診、聞診、問診、切診までで2つの証を立て、脈診により証を最終確定、2つの証を左右に振り分け鍼治療に移る。実技では、腹診図を示しながら本証、副証を確認。肺虚・肝虚の相剋調整の鍼を太淵、太白、太衝に行い「接触から押し付け、わずかに刺入し補う」とアドバイスした。ナソ・ムノ治療についても実演してみせた。
視覚障害者支援委員会企画の実技セッション『小里方式―刺鍼技術の検証方式で見えない世界を診る』では、視覚障害があっても経絡治療を学べる東洋はり医学会独自の修練法「小里方式」が紹介された。これは刺鍼者、検脈者、模擬患者の3~5名からなるグループで行う練習法で、検脈者は模擬患者の脈状を診て正確な取穴や刺鍼が行われているかを確認するもの。体験では晴眼者もアイマスクをつけ、講師の誘導でベッドや患者に触れながらぐるりと一周空間を確認し、問診、腹診、検脈を行った。

谷内秀鳳氏の実技

小里方式では講師が手を取り、感覚を繰り返し教える
シンポジウム『補法、瀉法の理論と技術―経絡治療の視点から』では、木戸正雄氏(天地人治療会会長)、中野正得氏(日本はり医学会会長)、橋本厳氏(経絡治療学会)、二木清文氏(漢方鍼医会)がそれぞれの立場から補瀉について語った。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事をシェアする
あわせて読みたい