ブラジルで鍼灸が法制化
2026.02.09
投稿日:2025.11.06
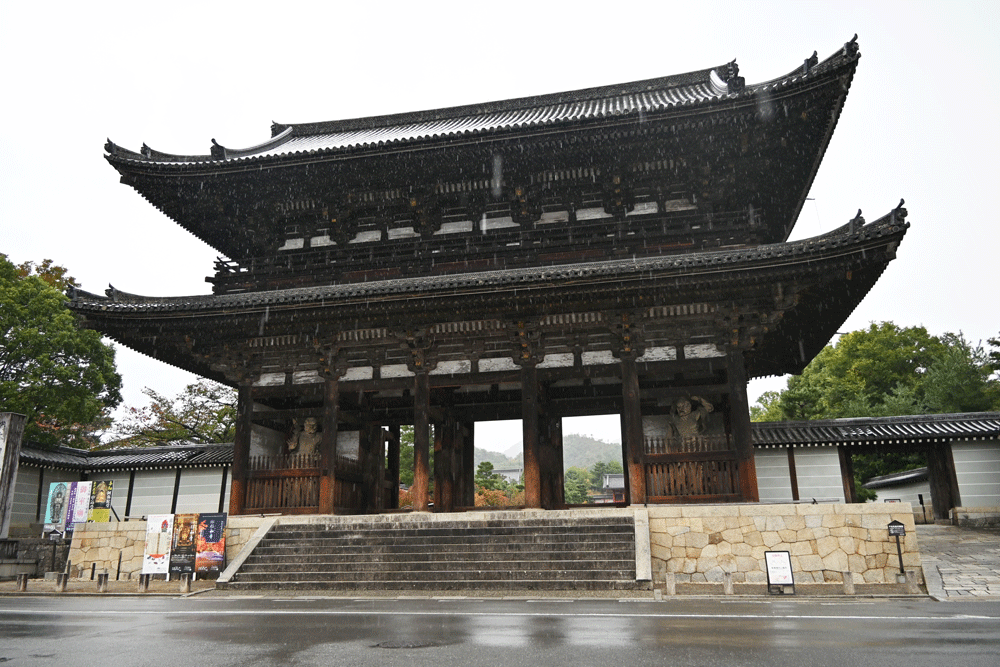
仁和寺はユネスコ「世界遺産」に登録されている
真言宗御室派総本山仁和寺霊宝館(京都市右京区)において秋季名宝展『国宝 医心方の世界―仁和寺の祈りと学び』が開催されている。日本最古の医学書で国宝の『医心方』や『黄帝内経』をはじめ、『本草綱目』『薬性論』『明堂之図』など多数の「医」に関する書跡をみることができる。会期は11月30日まで。
『医心方』は、当時の医療制度の中で医師同様に活躍していた鍼博士の丹波康頼(912~995年)が984年に編纂したもの。すでに失われた中国の医学書の内容を現代に伝える貴重な資料になっている。元は30巻あったが、仁和寺に残されているのは5冊の写本。原本に近いと評価され、通称「仁和寺本」として知られている。
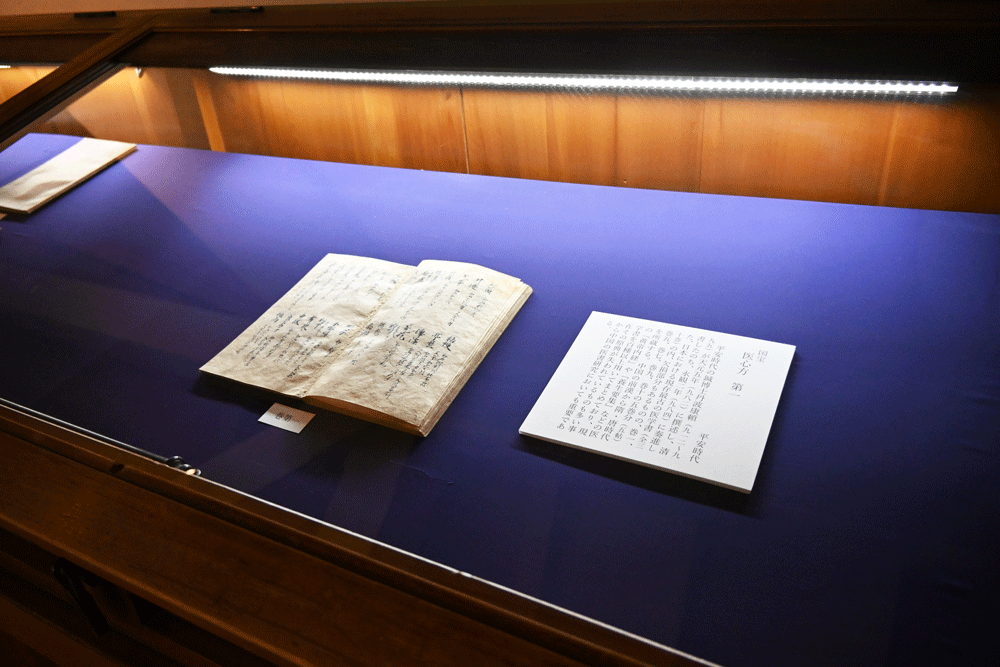
国宝『医心方』(平安時代前期)
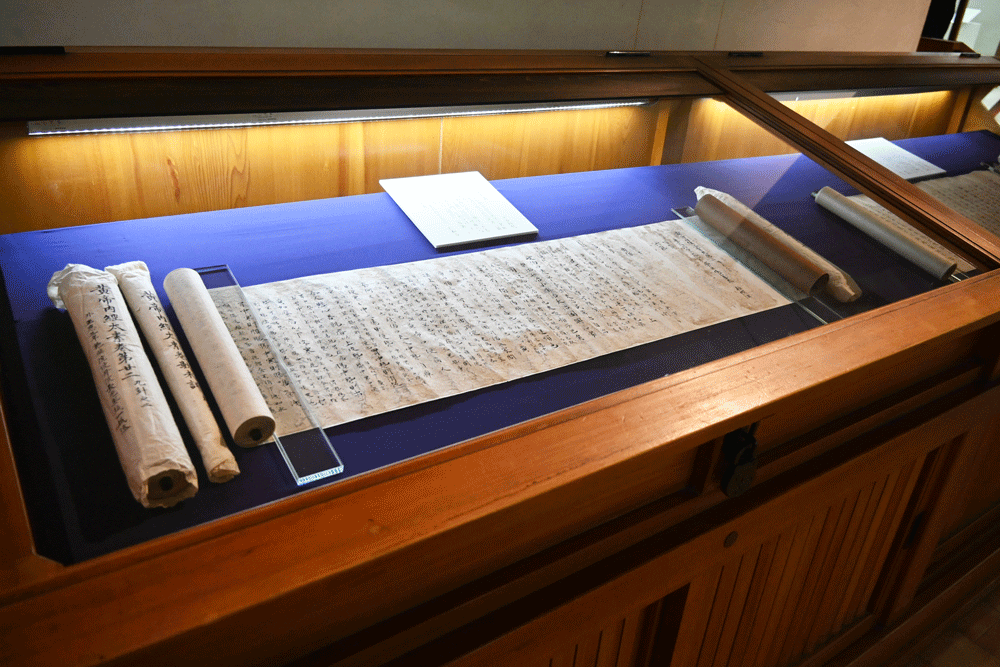
国宝『黄帝内経太素』(平安時代後期)、今回は初公開の巻を展示。文字のにじみから復元の難しさが分かる
仁和寺は古くから医療関係者と特別な関わりがあったと考えられている。
同寺が応仁の乱で焼失し、江戸時代に再建の指揮を執った僧侶顕證の日記には、「頭痛」の言葉が多くみえ、思い通りに進まない再建作業にストレスや、疲労、頭痛に悩まされながら奮闘していた様子をうかがい知れるのであるが、「医師より『半夏白朮天麻湯』を処方された」との記載も確認できる。実は当時は、医師より薬を処方してもらえるのは宮内に関わる身分の高い人のみのことであった。さらに同寺は、今回公開した書跡の他にも「医」に関する多くの典籍を保管している。

『顕證上人座像』(江戸時代)
館内をぐるりと一周し「医」「鍼」「法要」「薬草」「論」と、先人の知恵に触れる今回の展示では、内側は主に「医心方」をはじめ、伝統医療に関する資料が集められ、それを取り囲む外周では寺院が「医」のために何を行ってきたかを解説する。
『十二天像』の絵画を眺め本堂のしつらえをイメージしたり、国宝『御室相承記』の「孔雀経を転読したことで平癒した」との記載を確認したりと、人々の健康や平安が、「法要」や祈りによっても守られていたと感じられる。
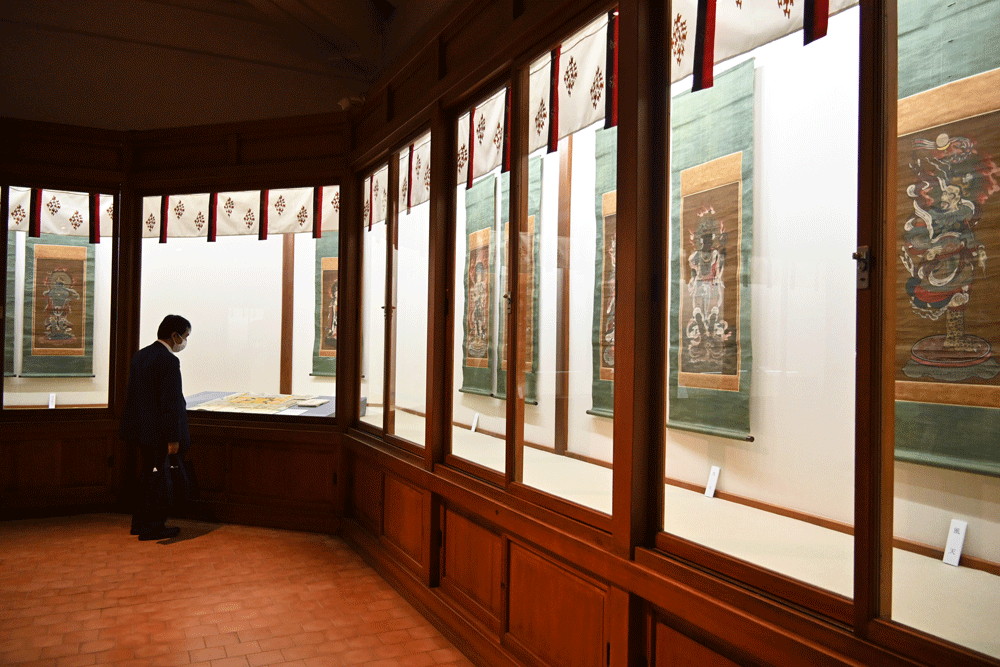
『十二天像』(江戸時代)
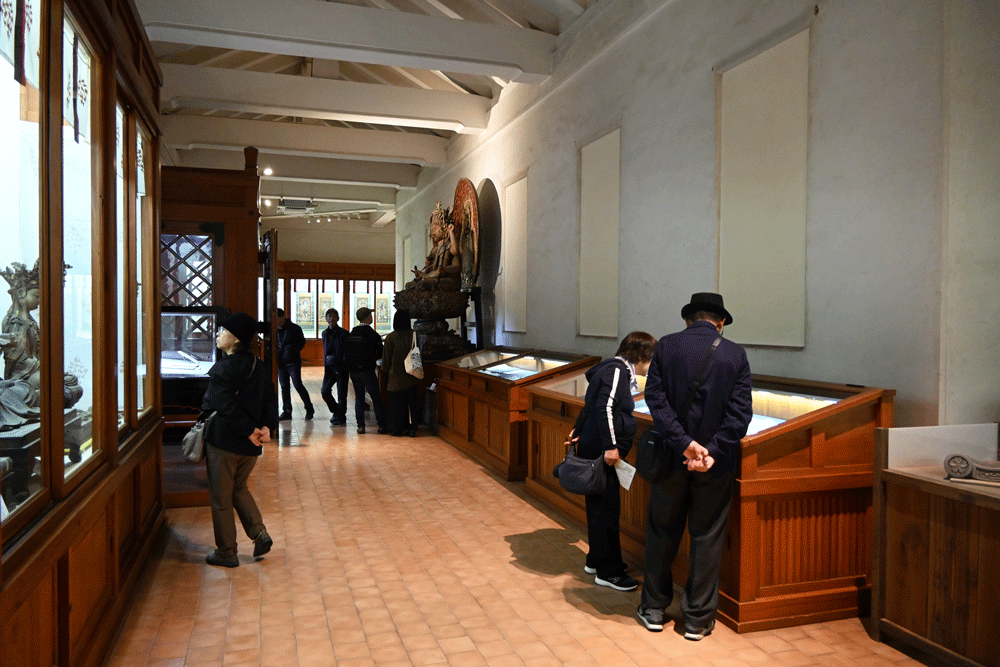
展示には、注目の表記を指し示すヒントが添えられているものもあるので探してみて。書き込みからは所有者の興味や疑問を知ることも
「これほど多くの医書を一度に展示するのは今回が初めて。ぜひ当時の『医』事情に思いを馳せてほしい」と語るのは、展示をディレクションした朝川美幸氏(同寺財務部管財課課長)。紅葉も始まるこの機会にぜひ足を運んでみてはいかが。
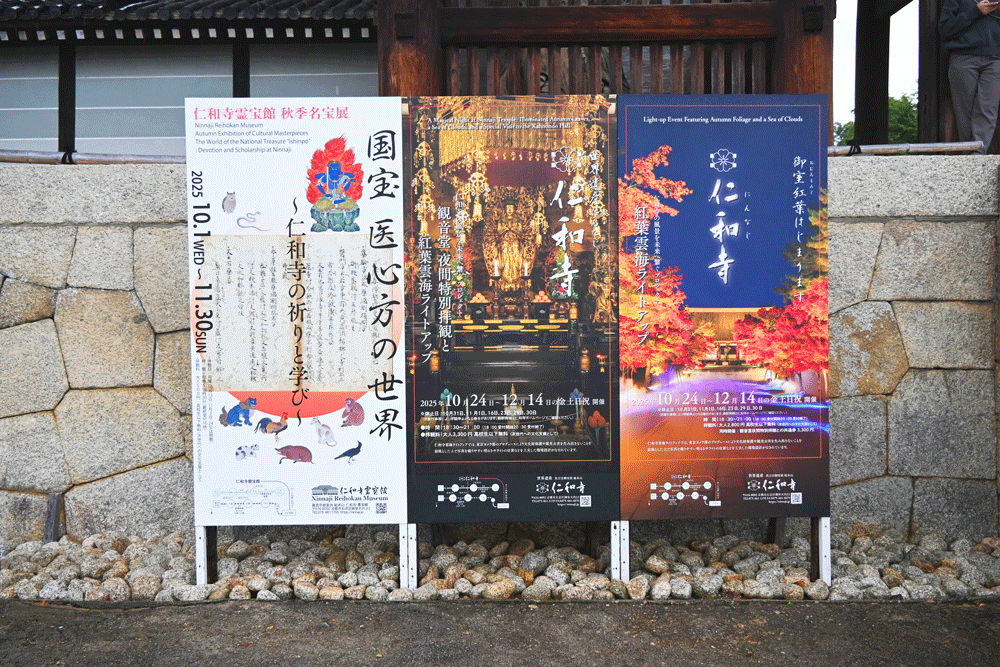
紅葉でにぎわう秋の仁和寺は催しが目白押し
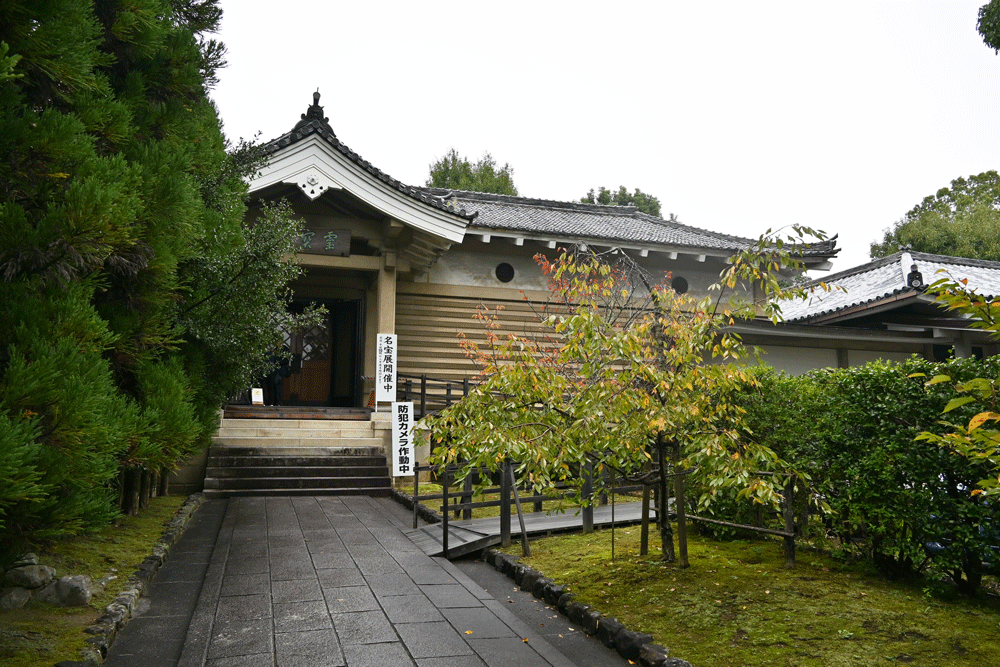
2026年に完成から100年を迎える霊宝館は、建築家・片岡安の設計で国の登録有形文化財に指定されている
真言宗御室派総本山仁和寺
京都府京都市右京区御室大内33
霊宝館秋季名宝展 10月1日(水)〜11月30日(日)
詳細はこちら
※会期中は展示の目録は変わらないが、文化財保護の観点などから展示個所の入れ替えがあることに注意。
この記事をシェアする
あわせて読みたい