ブラジルで鍼灸が法制化
2026.02.09
投稿日:2025.08.08
第30回日本緩和医療学会学術大会(会頭:田村恵子氏/大阪歯科大学)が7月4日、5日に福岡市内にある福岡国際会議場で開催され、がん患者における鍼灸治療についての講演や体験会が行われた。
今回初めての試みとなる日本緩和医療学会と公益社団法人全日本鍼灸学会の合同シンポジウム『緩和ケアにおけるがん患者に対する鍼灸治療の現状と今後の展望』において、緩和医療における鍼灸のメリットや課題が話された。座長を務めたのは、石木寛人氏(国立がん研究センター中央病院)と山口智氏(埼玉医科大学)。
山下仁氏(森ノ宮医療大学)は、鍼灸は伝統療法ゆえ科学的検証は遅れていたが論文は増加傾向にあり、2024年末時点で国内の19の診療ガイドラインにおいて28の推奨に関する記載があると伝えた。肯定的な推奨は疼痛や脳卒中後の肩手症例群など18あり、病態によっては日常臨床以上に慎重な感染症対策が不可欠となる。
鍼灸が評価されにくい理由として、無治療との差は明らかでも偽鍼は刺激による効果が出てしまい真の効果との差が検出されにくいと話した。また情報源に関し、健康情報全般はテレビやインターネットが主流なのに対し、鍼灸は医師の勧めや口コミが多いとの調査結果を示し、医師の理解を深める努力とともに、専門知識を身に付けた鍼灸師が施術する必要性を強調した。
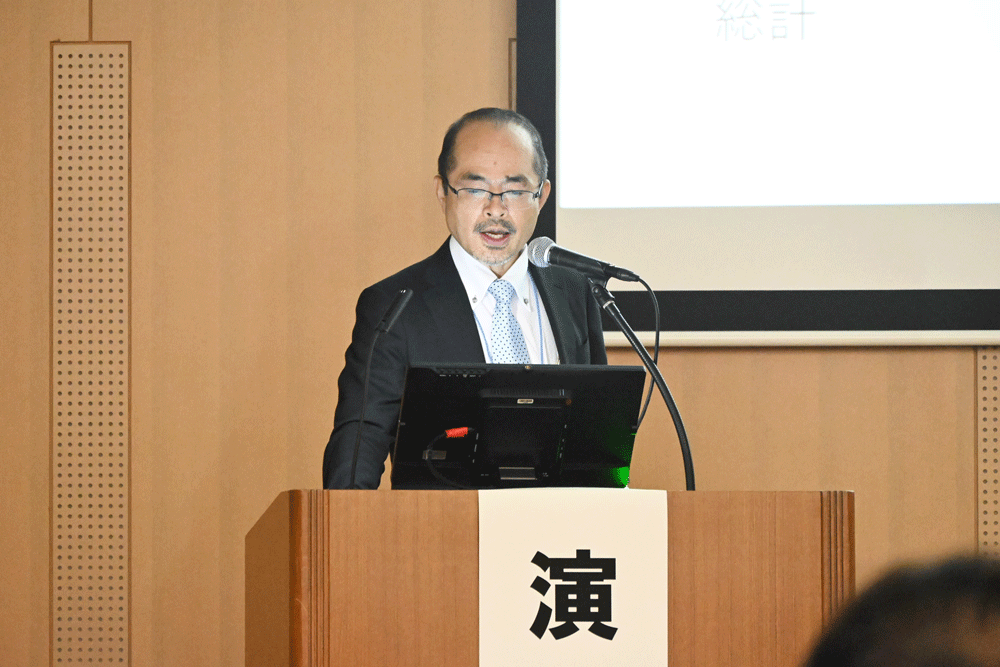
山下氏。全日本鍼灸学会の立場から
萩原彰人氏(国立病院機構埼玉病院)は、鍼は日英の慢性疼痛診療ガイドラインにおいて推奨されていると示し、下行性疼痛抑制系の賦活などによる鎮痛作用に優れていると説明した。緩和ケア病棟の患者に対しては、痛みに苦しむ中での侵襲刺激の敬遠や、出血傾向などから接触鍼が有用だと紹介。医師である自身が刺さない鍼に興味を持ったのは、化学療法誘発性末梢神経障害(Chemotherapy-induced peripheral neuropathy : CIPN)に対し、有害事象なく、ほとんどの被験者が大きく改善した小川恵子氏(広島大学病院漢方診療センター長)らの研究結果に驚いたからだという。小川氏の在籍する病院では鍼治療を提供し、外来では不定愁訴、がん疼痛、化学療法の副作用を、病棟では悪心、倦怠感、食欲不振、全身痛、呼吸困難など緩和ケアを中心に行っている。
病鍼連携が望まれるが療養費の問題などがあるほか、さらなるエビデンスの構築や医学部での卒前教育、鍼灸適応の明確化など、医師と鍼灸師が顔の見えるコミュニケ―ションのもと課題に取り組むべきと訴えた。

萩原氏。日本緩和医療学会の立場から
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事をシェアする
前の記事
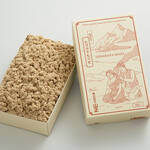
あわせて読みたい