ブラジルで鍼灸が法制化
2026.02.09
投稿日:2025.08.06
第二回医療功夫(いりょうカンフー)学術集会が7月13日に森ノ宮医療学園専門学校アネックス校舎(大阪市東成区)で開催された。
代表の奥圭太氏は「体を養い鍛えていることを医療に発展させる方法を、これまで実践してきた先生に聞き、皆で考えたい」と伝えた。「現代と伝統の交流」とのコンセプトのもと、当日は匿名で参加できるラインのオープンチャットを開設し、投稿されたコメントもふまえ議論の内容を決めていく参加型の学会となった。また、学会用にChatGPTをカスタムした独自AI「シャオフーちゃん」をリリース。参加者はそれぞれの端末で武術や中医学の疑問を解決しながら講演を聞いた。
葛西眞彦氏(易簡太極拳推手発展協会)は太極拳の型のひとつ「小太極」を、治療家の感受性の鍛錬にもなるとして教えた。足を前後に開き、手の動作とともに重心を前後にゆっくりと移動させながら、全身が連動して力まず動かせる最適解を模索する。練習を積むことで相手の力みや反応に繊細に気づくことができる「感覚センサー」を磨くことができ、治療家が患者を診る能力の向上にも応用できるという。講義は体験型で進み、参加者は体を動かしながら感覚を確かめた。
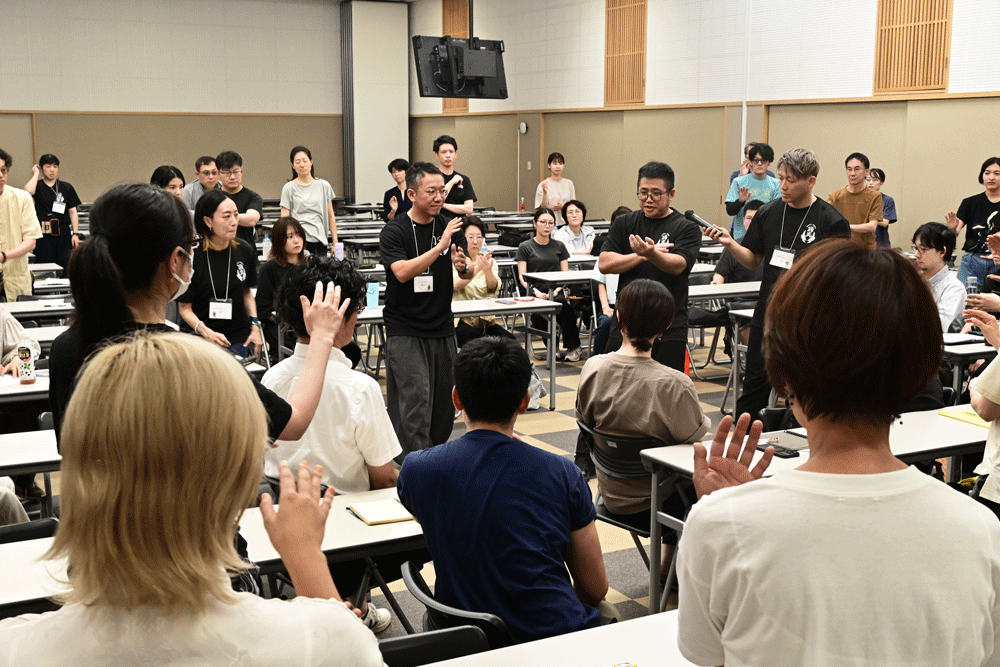
中央で動作の手本を見せているのが葛西氏、その左はナビゲートを務めた鋤柄誉啓氏(お灸堂)、挟んで右は奥氏
李立祥氏(天津中医薬大学)は、専門としている医療と功夫の融合について
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事をシェアする
あわせて読みたい